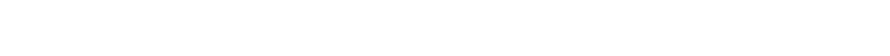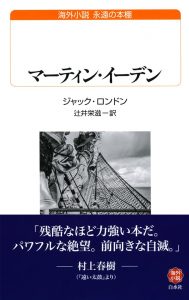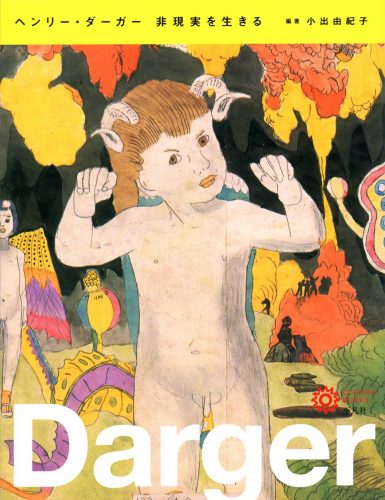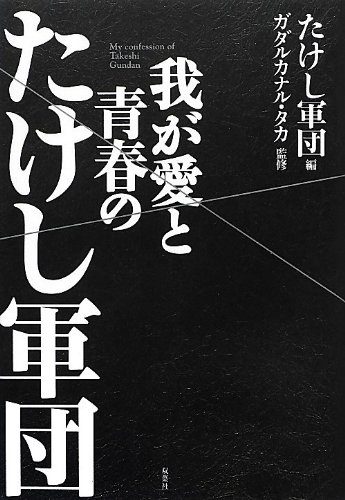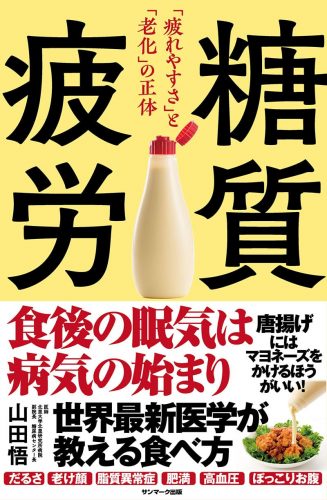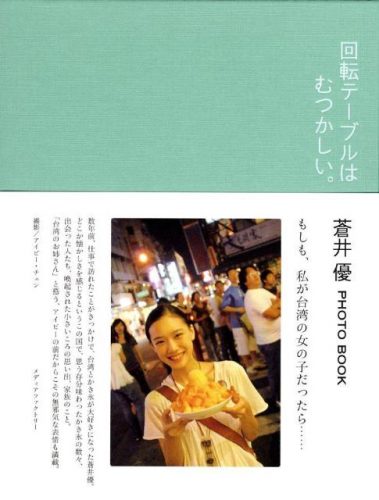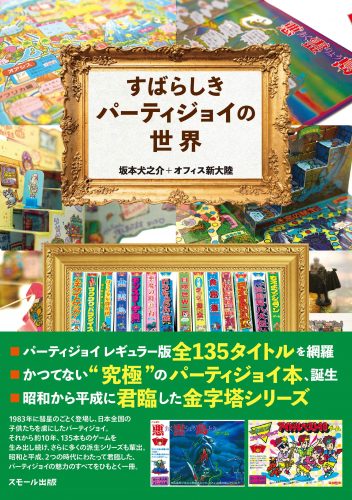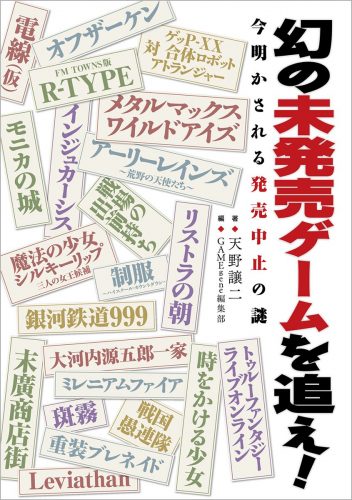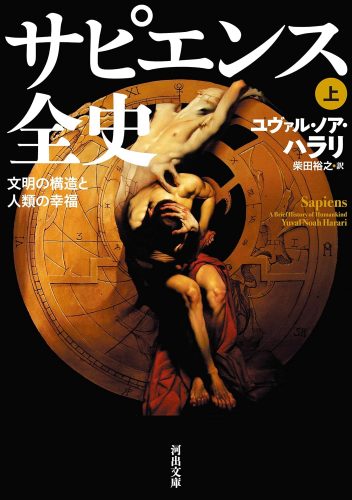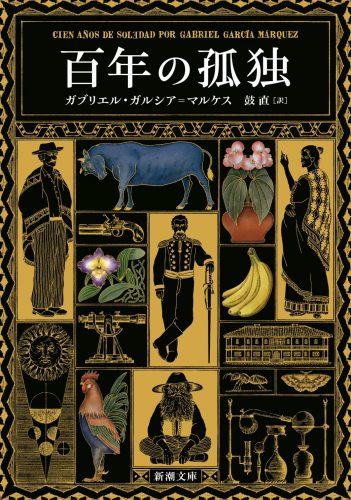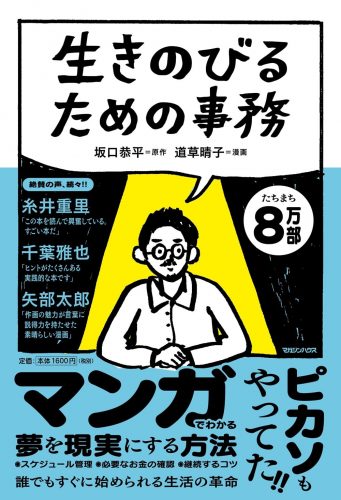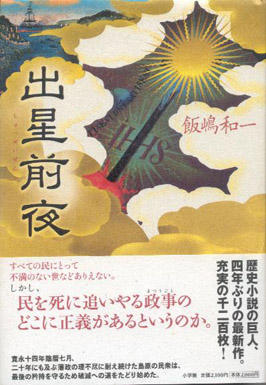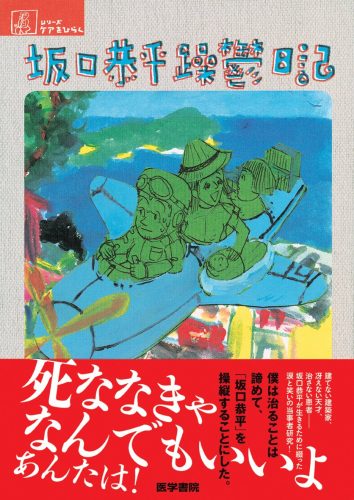もし本というものに生命力というパラメータが存在するとしたら、地球に隕石が降り注ぎ世界が荒廃に向かっても、この本は変わらず輝きを放ち続けていることでしょう。
労働者階級の男が、乾いたスポンジが水を含むように上流階級の知識や書物や哲学を吸収し、自分の中にある出来事や愛や芸術を文字で綴れば素晴らしいものになるという確信と、世間や貧困や周囲の無理解との戦いの物語。
一日5時間睡眠で、起きている間はずっと勉強と執筆。
すべて独学で。
学校は進捗が一番遅い人に合わせるから非効率であること、執筆には必要のないものを勉強しなくていいことを無学の身でありながら彼は心得ている。
そして大学生の学力を1年も立たずに超えていく。
そして彼は貧困に苦しみながら、起きているすべての時間を執筆に充て、成功するために小説の投稿を続ける。
ときには投稿のための切手代すら捻出できないほどの飢えや、執筆を断念して数ヶ月の出稼ぎに出ねばならない場面にも直面する。
全編面白かったですねえ。
520ページというかなりのボリュームなんですけど、ずっと面白かったですねえ。
人生でいちばん面白かった小説かもしれない。
この本が書かれたのは1907年で、すでに100年以上前なのに古さはまったくなく、ただひたすらに面白かったです。
面白さにびっくりした。
寝たくないって思った。
アドセンス336×280レクタングル(大)
関連記事
Hanako特別編集 センスのいい部屋、74人のアイデア。 Hanako
マガジンハウスは部屋の本がうまいですよね
Hanakoがベースなだけあって、単なる部屋の写真の羅列ではなく、
どういうふうにインテリアを配置したらセンスが良くなるか、という実用的なところに重きをお …続きを見る
我が愛と青春のたけし軍団 ガダルカナル・タカ
世間では「ビートたけしの金魚の糞で無能無芸の能無し集団」と誉れ高いたけし軍団。そんな彼らにファンはいるのかと言えば僕のように「ビートたけし大好きだけど、その偉大なる師匠の下で生息していた軍団の生い立ち …続きを見る
すばらしきパーティジョイの世界 坂本犬之介, オフィス新大陸
私、レトロゲームのグッズを買うのが好きで。初代ファミコンのマリオとか、SDガンダムとか。そういった、レトロゲームのグッズをメルカリとかで漁っていると、パーティジョイっていうボードゲームをよく見かけるん …続きを見る
サピエンス全史 ユヴァル・ノア・ハラリ, 柴田裕之
ひとは生まれながらにして罪を背負っているっていうのは本当のことかもしれないね
人間の誕生から現代に至るまで、人間はどのような生活を送り、どのように発展し、どのように……と、人間にまつわる無数のど …続きを見る
百年の孤独 ガブリエル・ガルシア=マルケス, 鼓直
大ブームですね
ヨーロッパかどこかのとある血族を描いたSF小説
核心的なネタバレではないんだけど、ちょっと内容を書くのでご注意ください
ただの民家がポツポツと点在していただけの土 …続きを見る