民俗学者の宮本常一さんが明治~戦前に生きた人たちへのフィールドワークをまとめた本
電気もラジオもないような田舎の人々は毎日どのように暮らしていたのか、人々がそれぞれの地に定住するきっかけはなんだったのか、いまではもうなくなってしまった風習にはどのようなものがあったのか、村が発展していったきっかけはどのようなものがあったのか、村の集まりや祭りにはどのような意味があるのか、村の意思決定はどのように行われてきたのか、夜這いとはどのようなものだったのか。教科書には載っていない、日本のリアルな近代史
宮本常一さんはこのようにフィールドワークに基づいた本を多数出していて、
各本を読むことでいろんな年代や地域の情報が補完できるようになっているので、他の本も併せて読むことを強く推奨します
今年、能登半島で大地震が起きて、外野からは「人が住むべき場所じゃない」っていう意見もあって、実際にもう能登半島に住むことを諦めた人も多数いて
そしてまだ残っている人に対して「そこは住めないから早く出ろ」と無責任に言う人もいて
でも能登半島から人がいなくなるということは、その地の歴史を伝承する人がいなくなるということでもあって
いま、都会への人口の集中が起きているのは交通の便が良くなったというのがあって
かつては道すらなく、隣町へ出るのも一苦労だったから、その地に居ざるを得なかったというのもあって
本に載っているのも失われた歴史だけど、今も歴史って失われつつあるなとか、日本人は日本のことを知らなすぎるよなとか、そんなことを思いました
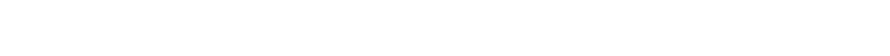

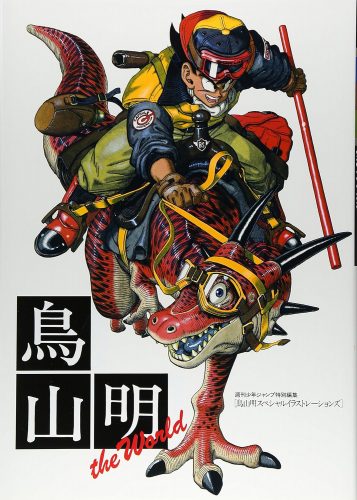

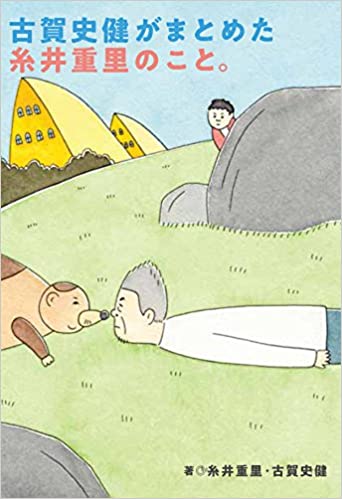
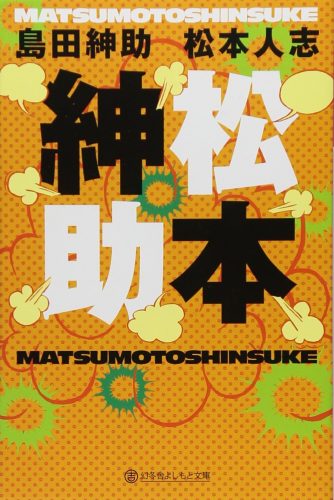
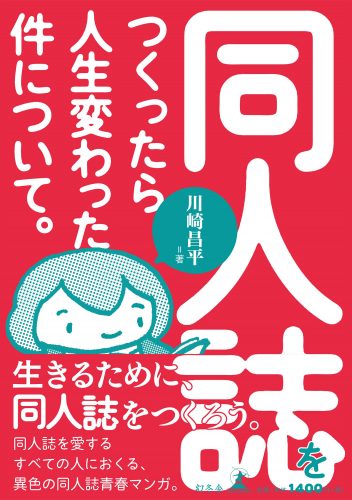
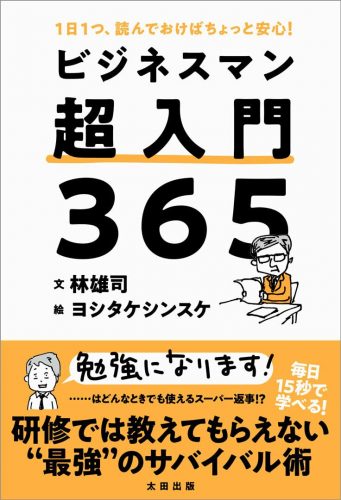
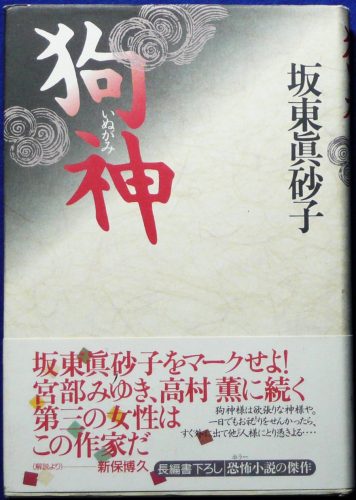
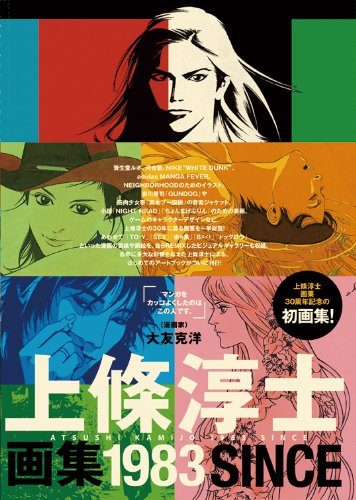
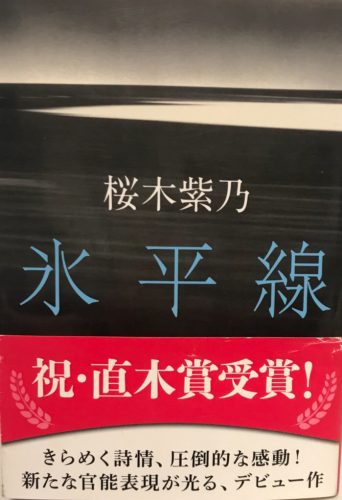
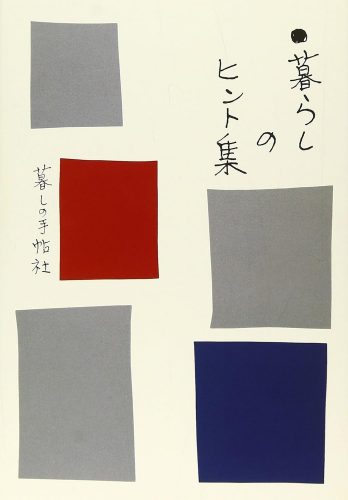
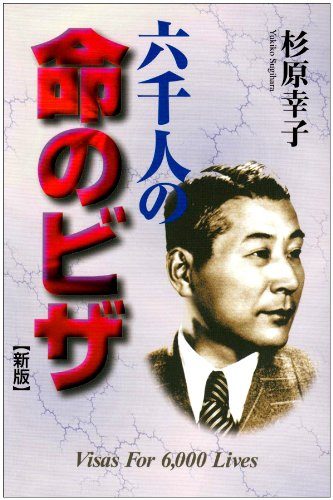
![BRUTUS 2018年2/15号No.863[山下達郎のBrutus Songbook] BRUTUS 2018年2/15号No.863[山下達郎のBrutus Songbook]](https://hondanabooks.com/wp-content/uploads/2023/12/81MOgKN6NeL._SL1500_-363x500.jpg)