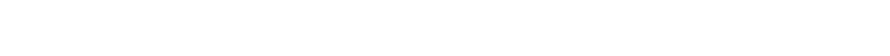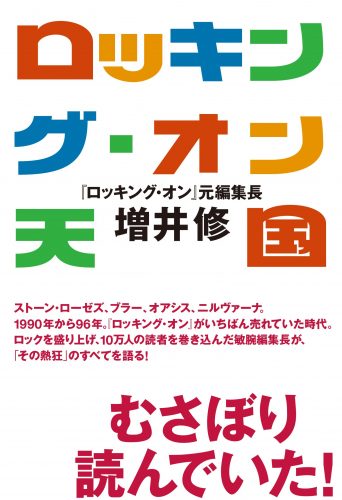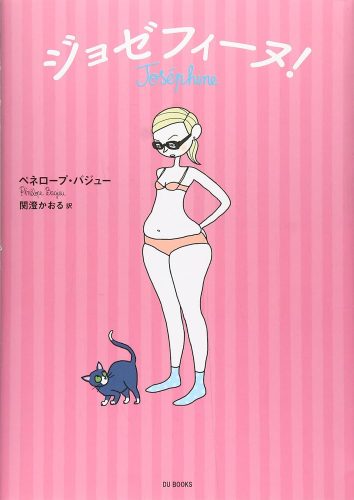実にいまから60年近く前、1964年に刊行された書籍が何度か形を変え、2011年に文庫化されたものだ。初版の刊行から数ヶ月後に東京五輪が開かれており、沖縄の日本返還はこれからまだ8年も先のことだ。こうした古い本だが、著者の平易な書き口や社会を見る目の的確さのおかげで古さをまったく感じさせないものになっている。高度成長期などとまだ名付けられていなかったその当時の状況を的確に描写することで、その後の大都市と郊外、ニュータウンを予感させる記述から始まる。
本書はまず、戦後復興しつつある東京、府中市の郊外での著者の暮らしぶりからはじまる。1962年の大晦日の夜、古くからその辺りに暮らしてきた人たちは大国魂神社に参詣に行くが、戦後の引揚者のために作られた町外れの新興住宅地はひっそりしている。里帰りしているか、寝静まっているのだという。そうして当時の東京の状況が描かれる。戦前に700万人以上にまで増えた東京の人口は戦中の急減から一転、戦後急速に増加し、1955年に800万人を、この頃に1000万人を超えた。さらに200万人増えるのはそれから40年近くたった21世紀になってからだ。そしてその人たちは全て、日本の田舎の村々から出てきた人たちだった。県人会、学生寮、お国訛り、郷土の名物、里帰り、満員の夜行列車に揺られての帰省…夜行列車か新幹線かという違いはあるが、60年前もいまも変わらぬ、地方から移り住んだ人々の東京での暮らしが描かれている。その人たちは誰もが、どこか東京になじみきれず、田舎との繋がりを保ち続けている。代々東京で生まれ育ってきた江戸っ子の暮らしはムラから移住してきた人たちに飲み込まれ急速に消えようとしているが、そうした変化が常に起きてきたのが江戸からの東京の歴史だったのだと。
そうして1960年代の都市を描いた著者は、日本の町がどうやって発展していったかをつぶさに見ていく。中世末期、京の都などから始まり江戸時代まで、ほんの小さな、定期的に村人たちが交易をするような市場の発生から商人町、城下町、宿場町、港町、門前町など…。町と言っても大きさはどれも知れていたから、同業者による取り決めもあり、秩序を守らねばならなかった。
そうした町と頻繁に、あるいはごくたまに関わっていたのが日本の村々だった。宮本によると10世紀にはすでに日本の水田は83万町歩になっており、これは昭和33年の337万町歩の1/4に達しているという。これを多いと見るか少ないと見るか…最も明治以後の品種改良、土壌改良、機械化などにより、いまでは単位面積あたりの米の収穫量は2〜5倍ほどになっているというが。
そうした奈良・平安の頃からのムラ、武士によって開かれいったムラ、ムラとムラの関係、境界などの争い、通婚や神仏を通してのムラの交流などが描かれ、最後にはそれぞれのムラの中の人々の暮らしが描かれる。村落共同体での家々の大小、親方と小作、分村、分家、産児制限、村八分…。そうした中で江戸から明治にかけて時代が進んでいくとムラにも様々な仕事や職業が持ち込まれ、かつては強かったムラの結束もゆるんできた。明治初年の3300万人の日本人のうち農民、百姓は3000万人いて、1960年代でもそれくらいの農民はいたが、高齢化し、ほとんどが兼業農家になり、専業農家は500万人ほどに激減している。今はもっと少ない。そして明治から昭和にかけての100年でムラには教育が行き届き、電気が通り、選挙も行われるようになり、劇的に変化したように見えるが、変化したのは出て行った次男三男が住む都会であり、ムラは未だなおムラのままだというのが、宮本の見るところである。
確かに日本の都市は都会的であるようで田舎っぽいというか、最先端のIT技術を駆使した企業でありながら、田舎の習俗のようなことを続けている場合がある。それは宮本がこの本を記した1964年と2020年代も、そんなに変わっていないのではないか。
/
2022/05/18