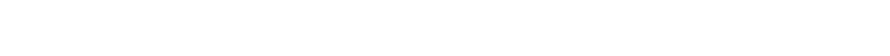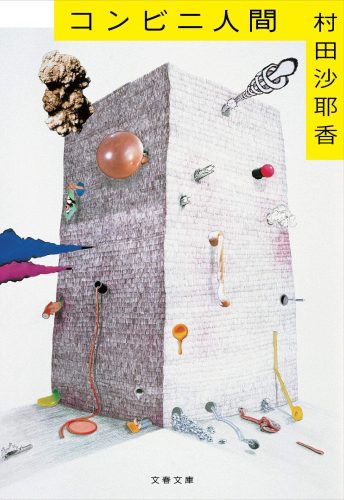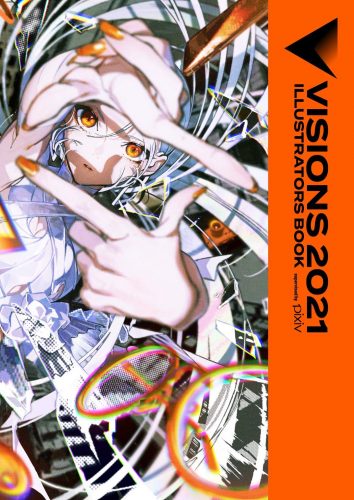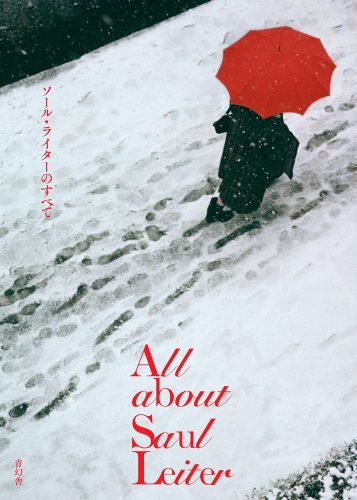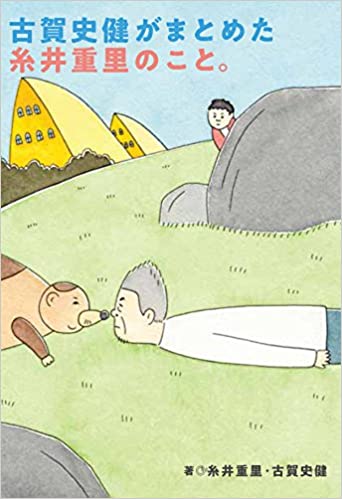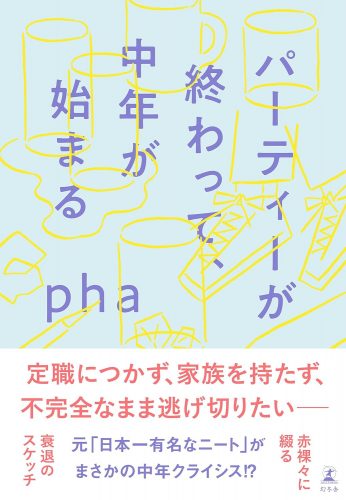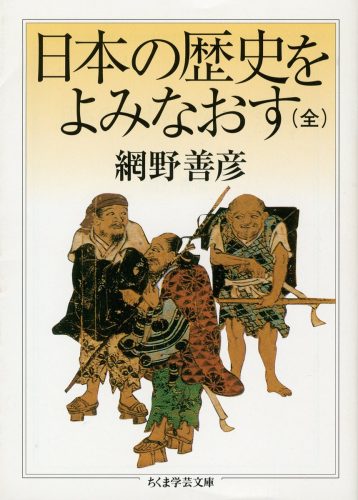常陸の国の北限、陸奥・磐城の伊達藩領と接する土地に暮らす郷士と村民が悲劇に見舞われる歴史小説。どの作品でもそうだが、著者は丹念に史料や時代背景を調べ、なぜ悲劇が起きたか、どう悲劇が進行していったかを実に細かく描写していく。悲劇は陰惨だ。村人たちがことごとく姿を消し、聖なる森とされている「山林」で惨殺されているという。時代は関ヶ原の直後。地元の大名・佐竹が秋田へ改易され、家康の息子が水戸に移ってくる。そのためこの年、ようやくこの地で検地が行われるのだが、それまでは伊達への備えとしてある種の独立した勢力を認められていた地侍たちにとって検地は初めてのことで、屈辱的であった。そしてその検地は古来より聖なる田として隠されてきた村の共有田の「御田」にも及ぼうとし…といった内容だ。
関ヶ原で勝ち、有無を言わさぬ農民支配を行おうとする天領の役人たちと、刀狩以降も兵農分離をしていなかった山奥の郷村の間に起こった悲劇。郷村では伊達への備えとして刀狩すら行われていない。役人と村人たちがぶつかるのは当然の帰結だったのだろう。佐竹の蔵入れ地でひたすら年貢を納めるだけの農民とは違う、自立した村人の暮らしや考え方、風習がよく伝わってくるが、文章が重厚で登場人物も多く読みづらいかもしれない。
なお、この事件は現在の茨城県大子町で「生瀬乱」として、200年近くたった19世紀にようやく取り上げられるようになった史実であろうが、一村全滅で証言者が残っておらず、起きた年代や内容も未だに明らかではない。
/
2022/04/05