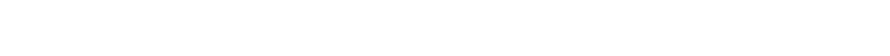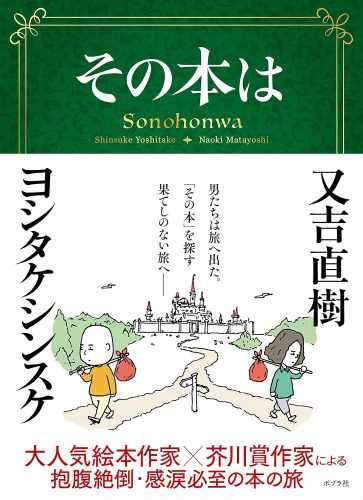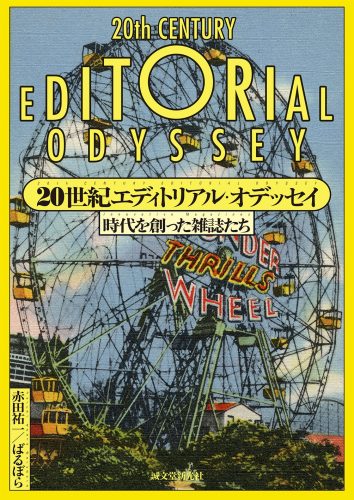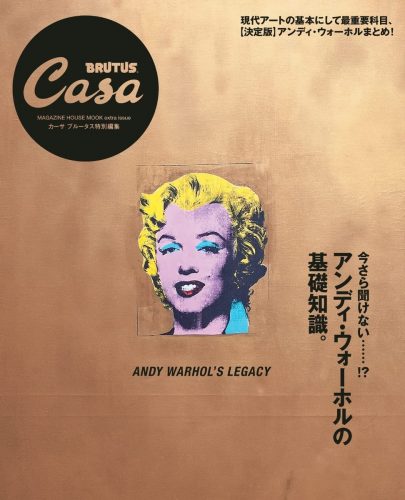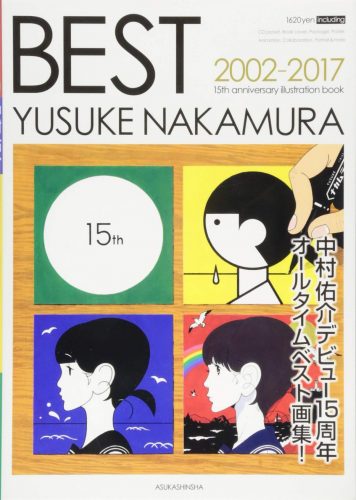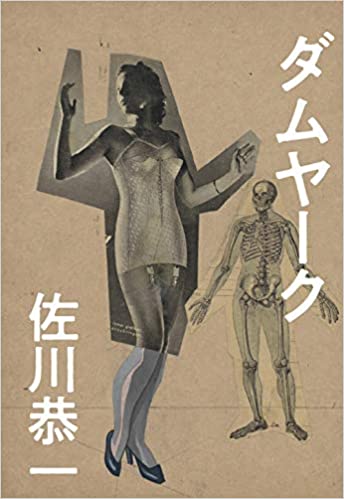映画化もされているベストセラーだが、つい最近まで内容を知らなかった。レンタル店にDVDが置いてあったのを何度も見たが、どうせ大したことのない邦画だろうと、なめてかかっていたのだ。だが中身を少し調べ、驚いた。元ハンセン病患者と社会の関わりを描いていたのだ。
主人公は、どら焼屋の雇われ店長。しがない中年男性で、人に言えない過去がある。その男に老婆が話しかけるところから物語が始まる。老婆は指が不自由だったが、じっくりと時間をかけてあんを炊き上げ、見事などら焼を作った。あんが評判となりどら焼屋は繁盛するが、老婆がハンセン病だったという噂が広まり…といったあらすじだ。
ドリアン助川はライブで地方を回っている時、元ハンセン病患者との関わりをもったという。そして時間をかけて取材し、この作品を書き上げた。ハンセン病患者に対する日本国の仕打ちは酷薄すぎた。強制隔離、強制断種。社会との関わりを許さず、特効薬ができて患者の病気が治ってもずっと隔離が続けられた。隔離が違法だとして裁判が起こされ、国が敗訴し、当時の首相・小泉純一郎が控訴しない決断を下したのは2001年。強制隔離がはじまって実に70年が経っていた。筆者が2020年に東村山の国立ハンセン病資料館に行った時も、まず1階で目についたのが小泉純一郎らの謝罪文とその後の補償法成立の流れを記した掲示物だ。
そんな重く苦しいハンセン病患者の人生について描くのは、ドリアン助川にとってもつらかったに違いない。だがラジオの人生相談で人気を得て以後、何をやってもうまくいかなかったドリアン助川だからこそ、必死に炊きあがるあんを見つめ続ける元患者のような、ある種の救いのような物語を描けたのだと思う。
物語はどら焼屋の前の桜の木が、再び満開の花を咲かせるちょうど1年で終わる。映画も小説同様によかった。映画の監督は河瀬直美で、『殯の森』でもそうだったが四季折々の樹木や木立を撮るのがとても巧みで、ドリアン助川と同様、表現というよりも、見つめ続けて、その見つめ続けたものを丹念に描き出すことが上手いのではないかと思った。