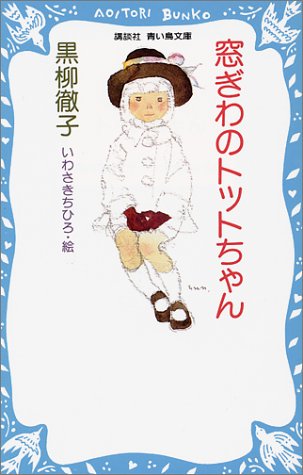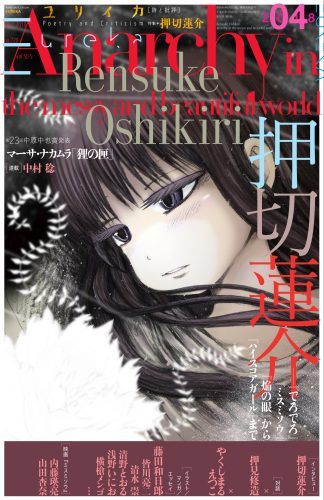日本で差別が生まれたのは何年からなのかとか、昔の日本人はほぼ農民だと思われていたけどそうではなかったとか、女性の地位が低かったのは大正~昭和だけだったとか、日本でお金の流通が始まったのはいつからだとか、日本の歴史の教科書には載っていない、日本の歴史を教えてくれる本
昔は穢多・非人というのは単なる職業で差別される存在ではなかった
古来の日本では死や血は汚れとされ、生理中の女性は穢れとみなされ、死者が出た家には30日間入ってはならなかった
死者や血に濡れた衣類を外に持っていってくれるのが穢多・非人の仕事で、町になくてはならない存在だった
それが室町時代に入ると穢多・非人そのものが穢れとみなされる風潮ができあがっていったという
当時の絵巻にも穢多・非人は堂々とした姿で描かれており、時代が変わるにつれだんだんと汚く描かれるようになっていく
また、日本人といえば士農工商という格付けがあり、日本人の大半が農民だったというイメージがあるが、これは百姓を農民と解釈したことによるミスだという
百姓は字の通り、百の姓(百の仕事)で、それを農民とひとまとめにしてしまったことで生まれた間違いとのこと
当時の資料を読むと、田畑がない土地では貿易船で儲けている百姓がたくさんいた
彼らは農民ではないのにもかかわらず、百姓=農民というくくりにされてしまったため、その後しばらく歴史の世界では農民としてカウントされていたという
学校で習っていないことばかり
僕らが子供の頃はいい国作ろう鎌倉幕府だったのが、いい箱つくろう鎌倉幕府になったように、
歴史のオセロがひっくり返されるその最前線の資料を読んでいる気持ちになる
とくに差別のことなんて教科書では絶対詳しく書けないもんね
日本人なら読んでおくべきです
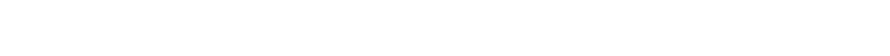


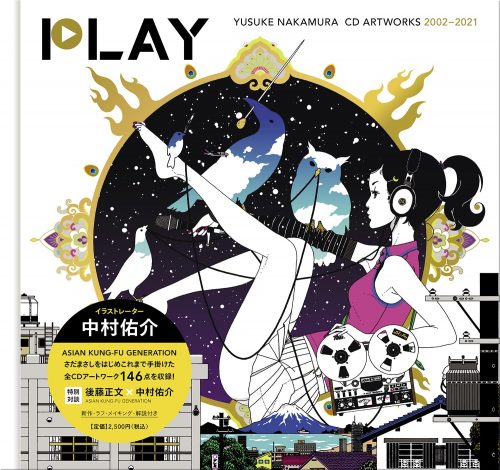
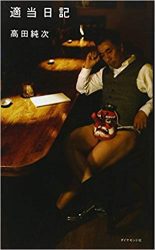
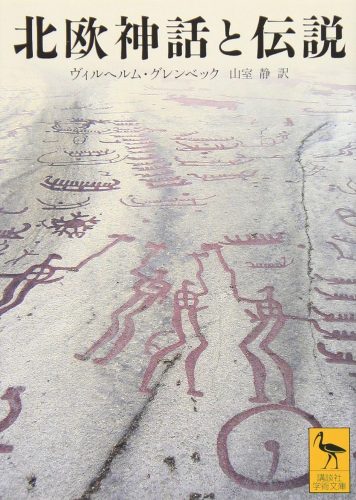
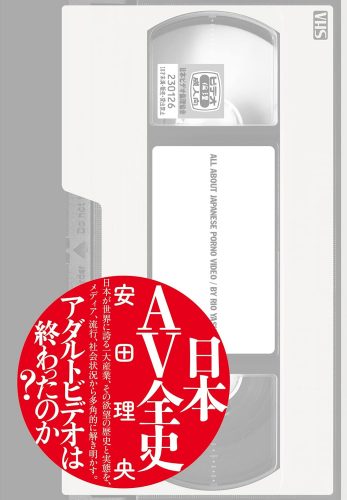

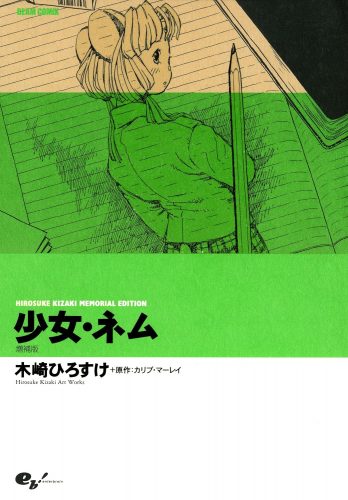
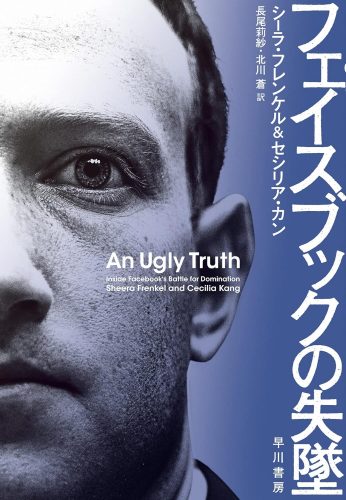
![BRUTUS 2022年 7月1日号 No.964[山下達郎の音楽履歴書] BRUTUS 2022年 7月1日号 No.964[山下達郎の音楽履歴書]](https://hondanabooks.com/wp-content/uploads/2025/01/711DGixxL1L._SL1500_-370x500.jpg)