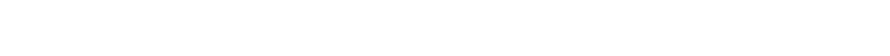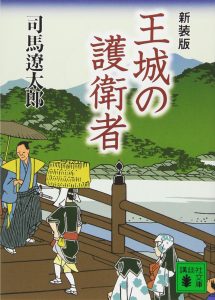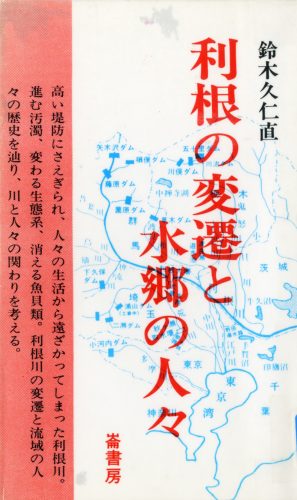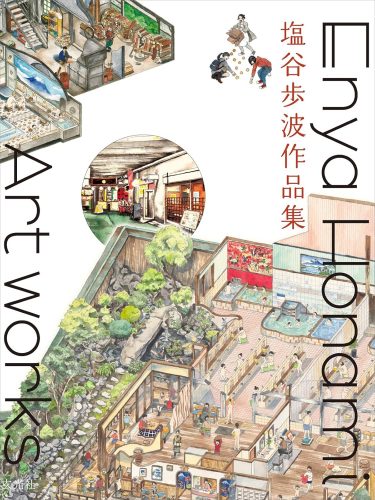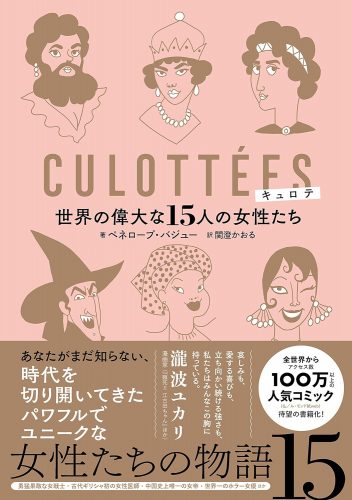『竜馬がゆく』、『燃えよ剣』などを新聞や週刊誌に連載中の1960年代半ばに、それらと並行して書かれた幕末ものの中編集。
表題作の「王城の護衛者」は京都守護職を命じられた松平容保の命運を、会津松平家の家訓や勃興とともに描いている。桜田門外で井伊直弼が襲撃されるなど開国後の混迷している日本にあって、公然と倒幕を目論む志士が潜む京都に赴くことは、家の断絶を意味し、事実そうなった。上洛後に京都の人々から歓迎され、孝明天皇からも練兵の天覧という名誉と信頼を得た一方で、身分制度上、浪士の捕縛といった実務を会津藩士が担うことはなく、かといって弱体化した京都の与力などはあてにできず、結果として新撰組がその実務を担うことになった。新撰組は浪士をことごとく斬り、会津松平は市中の人から恐れられ、維新を成功させる長州の憎悪の対象となった。松平容保の悲壮で数奇な運命の巡り合わせを見事に描いている。
「加茂の水」は幕末、薩長とともに維新を成功させた岩倉具視と、その老参謀の話。「鬼謀の人」は長州藩で軍制を改め、帝国軍の基礎を作った大村益次郎を描いている。この中編を読んだおかげで、靖国神社(実質は維新を成功させた長州藩の神社と言える)に大村益次郎の像がある理由がよくわかった。大村は維新後まもなく暗殺されているが、それ以前の活躍がいかに目覚ましいものだったか、よくわかる。大村のことはのちに『花神』という長編でも描いた。「英雄児」も、のちに『峠』として長編で描いた長岡藩家老・河井継之助について書かれている。「人斬り以蔵」は、他の作品にも度々出てくる土佐出身の郷士、岡田以蔵の短い生涯を描いた。
いずれの中編もわりと分量があり、1作でも読み応えがある。晩年の評論や随筆もそうだが、この時期の司馬遼太郎は実に多作だ。
/
2022/04/08