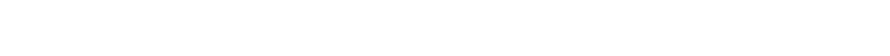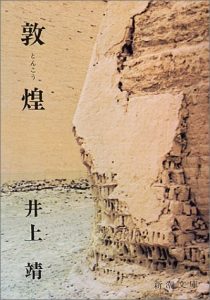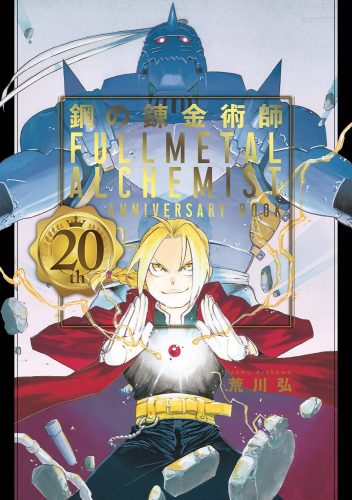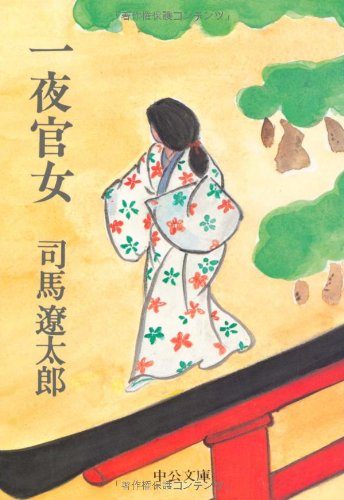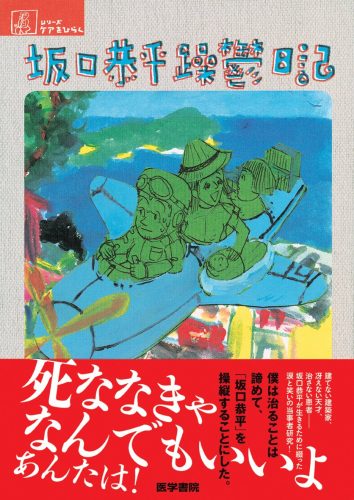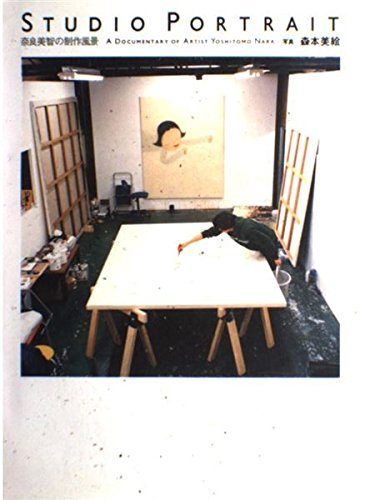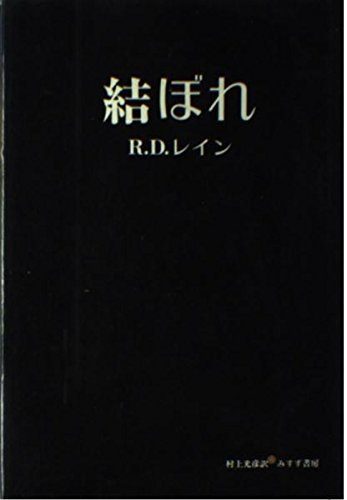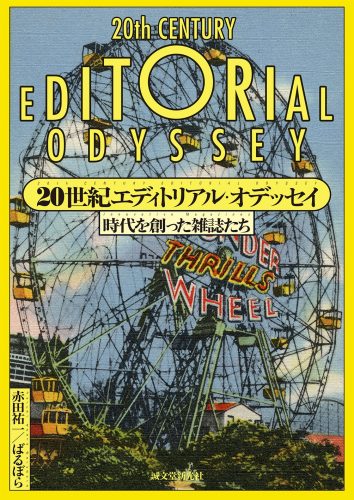シルクロードのオアシス都市を舞台に、国家の興亡と仏典の保存に執念を燃やす男…という内容なのだが、キャラクター描写がライトノベルのように典型的で、主人公たちの行動する理由付けも怪しいものだった。だが、この小説が大ヒットし、映画化されたり、その後のNHKの取材による「シルクロード」の特別番組も作られて大きなブームになったことは事実だ。今年になって『「敦煌」と日本人-シルクロードにたどる戦後の日中関係』という研究者の書籍も出ているくらいだ。
小説のあらすじは、宋の時代、科挙の試験に落第した主人公が繁華街で全裸の異民族・西夏人が売り物にされているのを目撃するあたりから物語が展開していく。女から与えられた布切れに書かれていた西夏の文字を知りたいと願い、西域に赴くも西夏軍に捕らえられ、一兵士となって過ごすうち、漢人の西夏将軍・朱王礼に見出され…といったあらすじなのだが、どうにも不自然というか、人物の行動も奇妙にみえてしまう。
もっとも敦煌の遺跡から何万巻もの仏典が発掘され、それがイギリス人やフランス人の探検家によって持ち帰られて保存されているという歴史的事実はあり(日本の浄土真宗本願寺派の法主も探検隊を派遣している)、なぜそれらが保存されたかという当時の出来事を作家の想像力によって描いているのだが、主人公が仏典の保存をする理由が、かつて主人公が交わり、見受けすると約束したものの身投げしてしまった異国の王女の菩提を弔いたいからというのは、どうもピンとこない。主人公は西夏軍の兵としてとオアシス諸都市の戦に身を投じ、何万もの戦死者や焼け出された難民が発生しているのだ。
とはいえ数百キロも続く単調な砂漠の道、そこに点在する緑のオアシスといった風景は日本人には馴染みがないものだし、ロマンがかきたてられるのは間違いない。東西南北、ざっと1000km四方が砂漠という風景は想像しようもない。しかしそういう地域を通して中国や日本に仏教や絹、宝石を運んでいた人々がいたことは疑いようがないのだ。敦煌(とんこう)とは文字どおり、敦にはあつく、煌にはきらめく、栄えるといった意味がある。かつて大きく栄え、巨大な石窟寺院が作られた敦煌は一度は行ってみたい場所だ。
/
2021/11/19