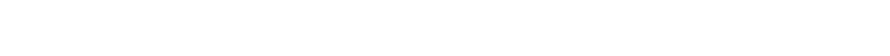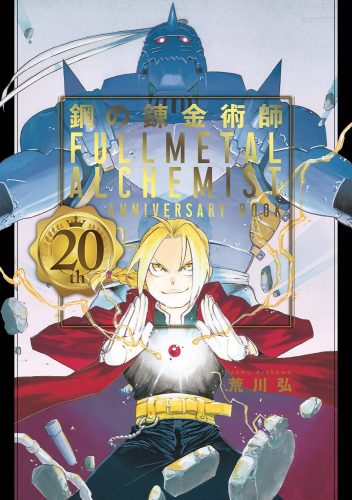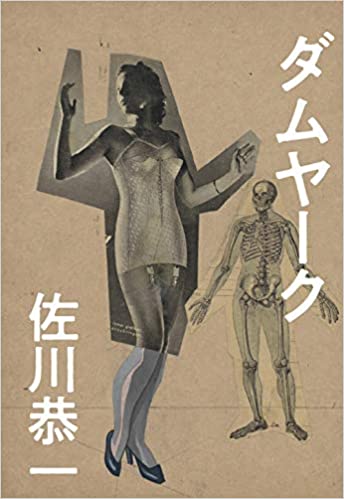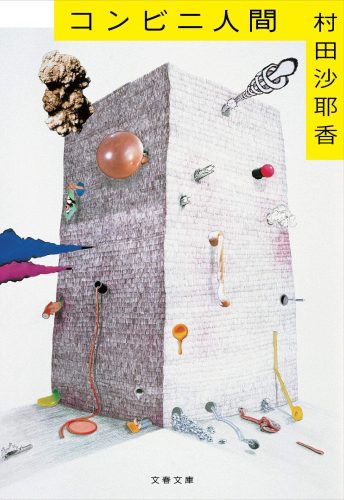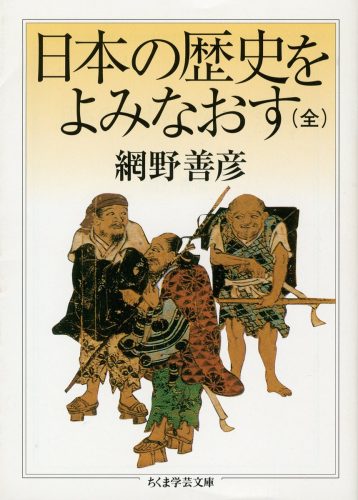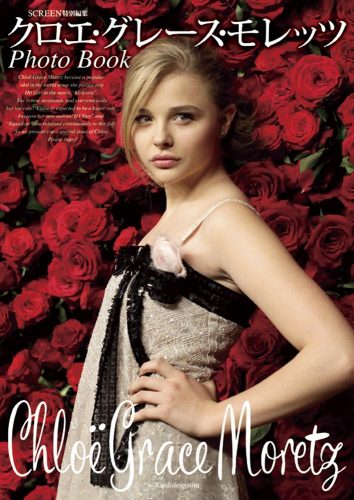圧倒的な描写の小説だ。奈良の中山間地、過疎の里山で農事に勤しむ70代の男が主人公だ。交通事故に遭い、植物状態のまま16年寝たきりだった妻を冬に失った年の梅雨から、翌年までの男の暮らしが、精彩に描かれる。男の暮らしそのものは地味だが、その暮らしや自然環境を観察する作家の眼差しと描写が実に細かく、情景を想起させる。取り立てて何か特別な出来事があるわけでもないが、季節が移り変わるにつれて、久しく会っていない兄が死に、そして久しく会っていない娘がまたニューヨークに赴き、そのため孫娘が一時的に滞在するなど、周囲が変化していく。だが男はひたすら、婿養子としてやってきた家の田畑や里山を守るように、土と向き合い続ける。自分が死んだあとは誰が守るのかわからないし、耕作放棄地になってしまうかもしれないが、少なくとも生きている間は、なぜ死んだ妻がこの土地で稲を作り続けたのかを問いかけるように、土と向き合おうとしている。
稲穂の生長の描写も細かい。葉がいくつでたか、何センチまで伸びたら補肥をやるか、出穂は何ミリか…そしてそうして稲や土と向き合うことで、生前の妻と語り合う。70代の男は少し呆けてきたのか、生者と死者の狭間が曖昧になってきているが、そもそも里山とはそういう土地であり、生者と死者が折り重なって毎年作物を収穫し、それを食べて生き、死んでいく。長年連れ添った妻は16年前、誰かと浮気をしていたらしく、それは狭い集落の公然の秘密になっていたし、男はいつの間にか、その妻の妹と暮らし始めるようになった。集落の近くの家で新たな生命が生まれ、ナマズや急逝した義弟の愛犬を飼うことになり、東日本大震災を経てもなお生死が折り重なった今と同じ暮らしが続くのかと思うと、突然物語が終わる。
初めから終わりまで、雨と水、霧や霜や水蒸気に満ちた土の物語だ。
/
2021/05/14