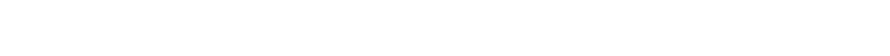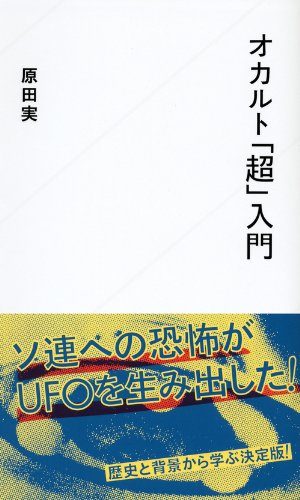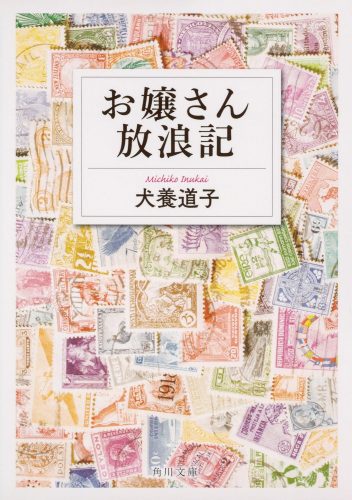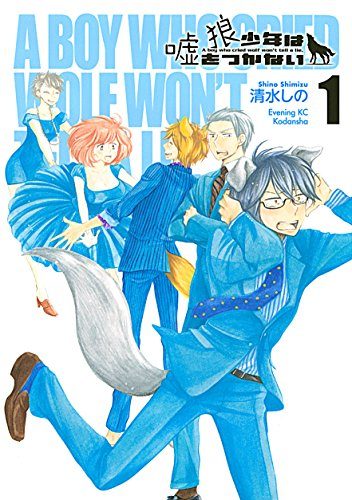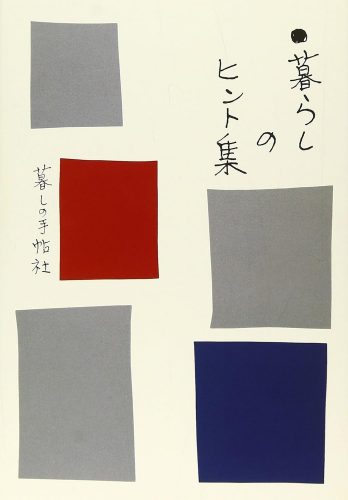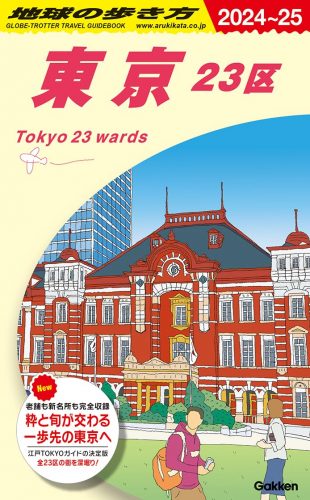リチャード・ブローティガンのなかでももっとも長く、小説らしい作品。
巻末に高橋源一郎さんのコラムが載っていて、高橋さんはブローティガンのなかでもこの『愛のゆくえ』が一番好きらしい。
舞台は図書館。といっても普通の図書館ではなく、個人が肉筆した世界に一冊だけの本のみを扱う図書館。主人公は24時間ずっとこの図書館の中で暮らしていて、3年間一歩も外に出ていない。
不器用な人たちが持ち込んでくる世界に一冊だけの本を預かり、書架に並べていく。ほかにこの図書館で働く人はいない。
その中でとある女性と出会い、妊娠させ、中絶のためにメキシコに行く。
この本の現題は『妊娠中絶 歴史的ロマンス1966年』。
でもこの本の主題は、閉鎖的な図書館にあるように思う。
この本の後半はずっと中絶の話だが、主人公はずっと胎児ではなく図書館のことを気にかけ、中絶手術後も日帰りで図書館に急いで舞い戻る。
誰が来るでもない、誰も本を読みに来るでもない図書館で過ごす時間を、仕事だからと割りきり、無意味に年齢を重ねることになにも気を払わない。
この閉塞的な空気をブローティガンは描きたかったのではないだろうか。
当時のアメリカの空気を描いたのではないだろうか。
ブローティガンが本気で小説らしい小説を書くとこうなるんだなあと思うと同時に、彼は文体の美しさを追う人なんだなと強く思いました。
小説から贅肉をそぎおとしていった詩の美しさを彼自身が誰よりも自覚していた。
だから彼は230ページの文庫本以上の長い小説を書かなかった。
ずっと閉塞的な小説でした。
あたかも自分自身も舞台の図書館にいて、ほこりを被った本を読んでいるような。