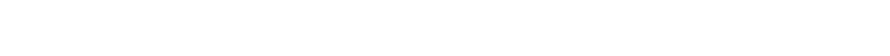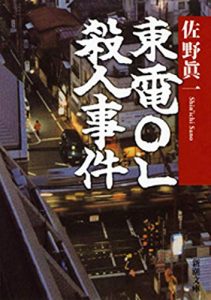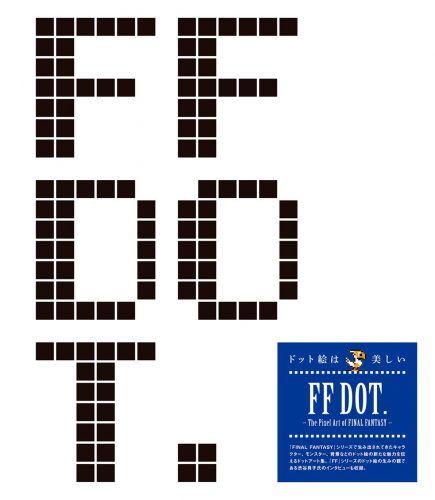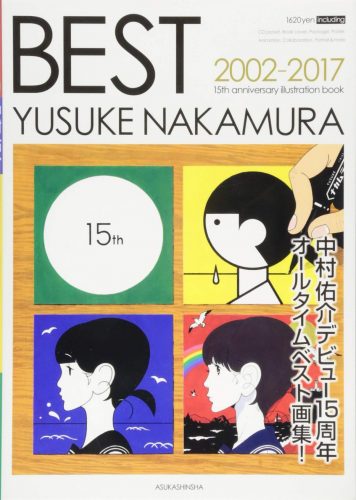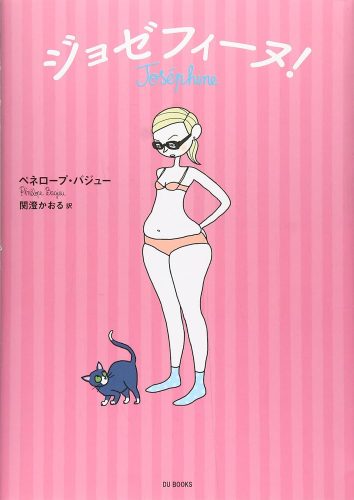ノンフィクション作家による事件ルポルタージュだが、まるで探偵小説のように書き手が行動というより、突っ走っていく。完全な公平中立という立ち位置は不可能なのだろうが、書き手は警察の稚拙な捜査をあげつらい、遠い異国で勾留され死刑になるかもしれないネパール人の無罪を信じて遠くネパールにまで取材する。そしてなにより、被害者の東電OLのプライバシーを暴く意図は全くないと言いながらも、その生い立ちや素性を暴き、その殺される瞬間まで頑なに売春を続けた真相に迫ろうとしていく。渋谷区円山町にホテル街が出来たきっかけとされる岐阜のダム建設とそれに伴う集団移住、そして被害者の父親の家系の山梨の墓など、一見事件とは関係のないような土地にまで赴き、そこかしこで被害者の幻影を見ていく。主観が多分に入り、時に偏見も入っているが、わからない謎を謎として提示してそれを追っていく執念は、それがたとえ好奇心によるものだとしても、ジャーナリストとして正しいのではないだろうか。
この事件は東京電力に勤務するエリートOLが、社内で挫折をしたのか、渋谷のホテル街で街娼となり、何者かに殺され、隣に住むネパール人が警察によって犯人にでっち上げられたという1997年に起きた未解決事件だ。ネパール人の冤罪は2012年に確定したが、この事件の犯人は未だに見つかっていない。
改めて読むと書き手の文体のせいか、平成9年に起きた事件だが、昭和の事件にようにも感じる。アムラーやコギャルといった20世紀末の平成・渋谷の文化が描かれる一方で近未来の無機質なビル群や昭和の残滓が色濃く残る元花街の円山町の風景などが描かれるが、一番の違和感は、当時目覚しく普及しつつあった携帯電話が登場しないことだろう。調べると携帯電話は1993年には200万台だった携帯電話普及率が95年には1000万台を超え、事件のあった97年には約4000万台に普及する。つまり携帯電話やメール、SNSなどが普及する直前の、そしてそれらが登場しない最後の事件だったのではないかということだ。
この事件と被害者が問いかける射程は大きい。事件から24年後の2021年になってもまだ女性の社会進出が声高に主張される。元東電社員だった父に憧れ入社するも、出世を実質的に閉ざされた被害者が自らを貶めるように街頭に立つようになったのか…。未だに誰もが浮かべる事件の疑問ではないだろうか。外国人への偏見も未だになくなるどころか、助長する動きすらある。
書き手の立ち位置を苦手とするひともいるだろうが、それなら自分ならどうこの事件を取材すればいいのか、読み手の立ち位置も問われるような作品だ。
/
2021/04/06