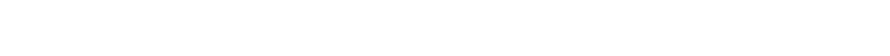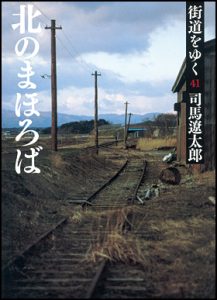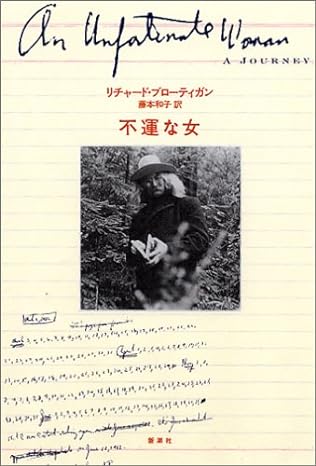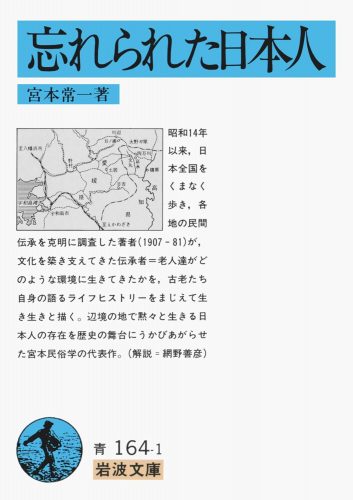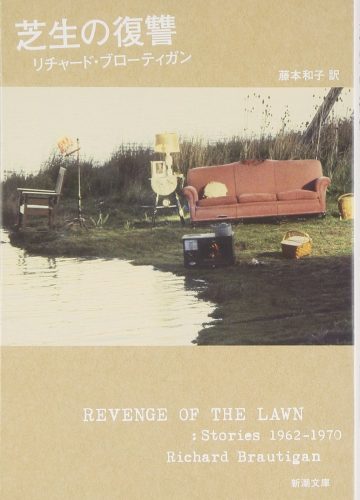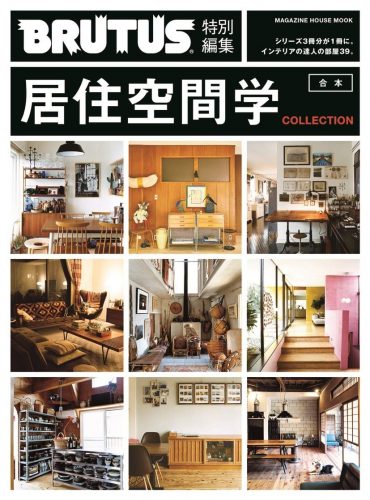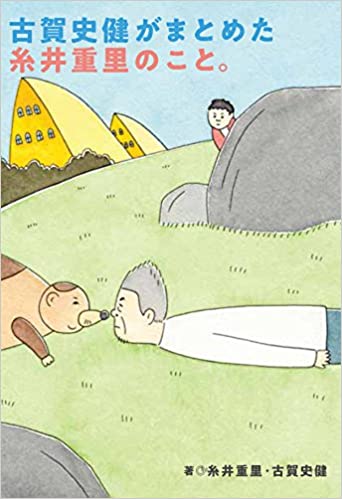1996年に亡くなった司馬の、94年の冬と夏の旅をまとめたもので、最晩年のエッセイになる。街道をゆくはこの後、三浦半島記と絶筆となった濃尾参州記のみで、一連のシリーズの中でもかなりの厚みがあり、それだけ司馬がこの地に愛着を持っていたことがわかる。地元でもよほどこの作品が好まれたのか、青森市にできた歴史資料館の名前にもなっている。ちなみにこの前は「台湾紀行〈40〉」、「ニューヨーク散歩〈39〉」と大きな旅が続くが、「台湾紀行」に劣らないほど長く、「ニューヨーク散歩」の2倍以上も厚みがある。
「まほろば」とは素晴らしい場所、住みやすい場所という意味の古語で、司馬が旅した時代、そして今なお新たな発見が続く縄文時代の巨大遺跡や交易で栄えた中世の港湾などを例に出し、いかに津軽、青森が人々にとって住みやすく豊かだったかを描いていく。
冒頭の「日本の新石器時代は、学者たちがヒトの暮らしへの愛を込めて縄文時代と命名した」という一文がとてもいい。かつての考古学者たちが縄文人を愛したように、司馬がこの土地とそこに連綿と生きていきた人々とその歴史を愛しているようだ。
旅は、主に青森県西部の津軽地方と、東部の南部藩領だった地域の下北半島に集中している。八戸あたりは「陸奥のみち 街道をゆく〈3〉」などですでに訪れている。道中、司馬は何度も青森からはるか北の北海道や樺太、そして朝鮮半島やロシア沿海州と、この地の交易がいかに豊かだったかを書いている。日本の中央政権から見れば青森は古来からずっと僻地だったし、青森の地方政権が交易の相手としてきた人々も、中国の歴朝から見れば僻地に住む人々だったが、彼らはそうした中央政権が知らないところで、お互いに豊かになってきたという。北方の諸民族は獣の皮で作る衣類に欠かせない鉄の針を欲しがり、青森の人々は北方の豊かな産物を求めた。今も鉄の産地として知られる青森や岩手の、いわゆる南部鉄は、下北半島の海岸で採れたという。
この紀行文には書かれてないが、昆布は甲状腺の病気に効くとして、遠く長江を遡り、中国の内陸部まで運ばれたという。一般的には清代に盛んになったというが、いつから行われていたかはまだはっきりと解明されていない。もしかすると司馬が空想した中世十三湖の港湾都市からはるばる運ばれたのかもしれない。
太宰治の小説や棟方志功の板画を交えながら、下北半島に移された会津の末裔や義経伝説、そして1991年の台風で大きな被害を受けたリンゴ農家の子供達の作文で締めくくられる。貧困や寒さに耐えながらも生き続けてきた青森の人たちへの深い共感にあふれた紀行文だ。