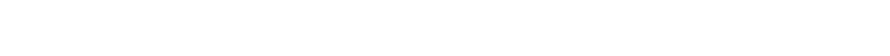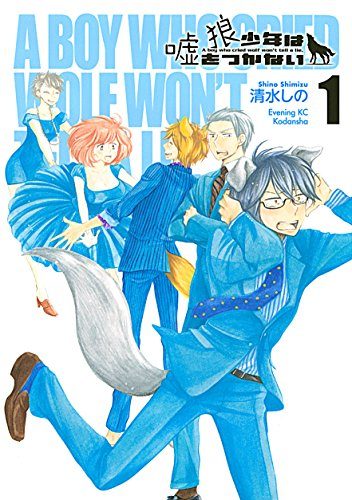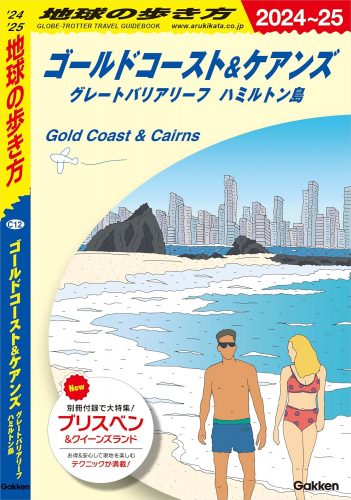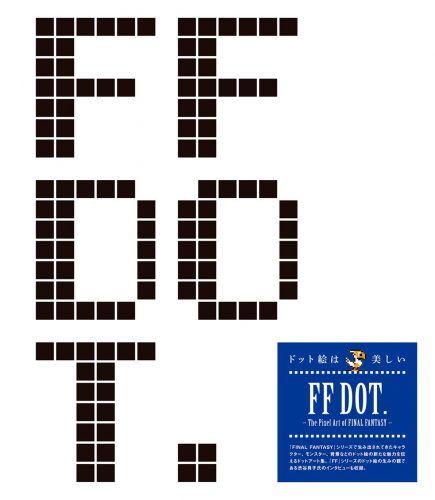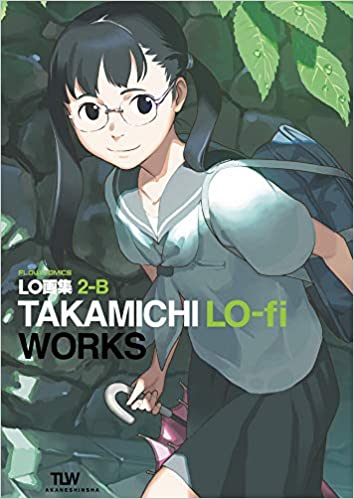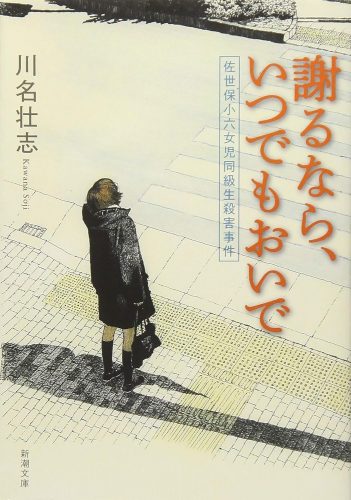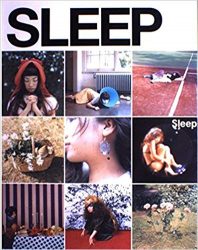自分はこれまで桜木紫乃の小説をいくつか読んでいて、北海道の風土をわかったつもりになっていた。たとえば直木賞受賞作「ホテルローヤル」は作者の親がラブホテルを営業したこと、そしてその名前の由来が箱に入ってデパートで売られていた初物のミカンからとられたことなどだ。ただそれだけだった。だが本書を読んで、北海道は、ミカンが生育しない土地なのだと改めて気づかされた。短編集の最後の「根無し草」では、新聞記者になった女の前に、かつて生家に上がりこんでいた山師が現れる。理髪店を営みながら儲け話に飛びつく父と、儲け話を持ち込む山師の過去の思い出、そして再び現れた老いた山師…。女は山師に両親は死んだと嘘をつく。実際は父は肝臓をやられ、母は糖尿病で入院していた。そして糖尿病の母に、父はミカンやリンゴを土産として置いていく。いまだに病気のことを理解していない父の描写も良いいが、道東ではミカンは自生できず、本土から運ばれてくるものだと改めて気づかされた。そういう風土なのだ。
どの短編も女が主人公だ。悲しく、たくましく生きている。桜木紫乃らしく、手に職をもった生き様が活写されている。そして北海道の暮らしがまざまざと描かれる。釧路川沿いの、冬には室内まで氷点下になりそうな安アパート、高台の瀟洒な洋菓子店、日本海側の牧場、留萌の小さな書道教室…桜木紫乃がファンだというストリップ劇場のダンサーも登場する。落ちぶれて、頼りない男たちとは違い、女たちはいつも運命を受け入れ、抗って、悲しい人生をたくましく生きている。北海道の暮らしが描かれている。
/
2022/02/09