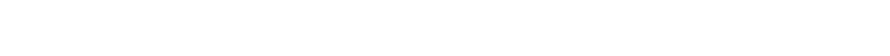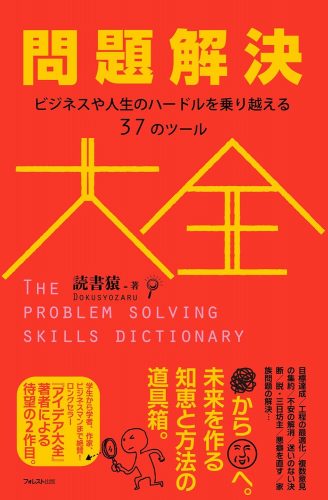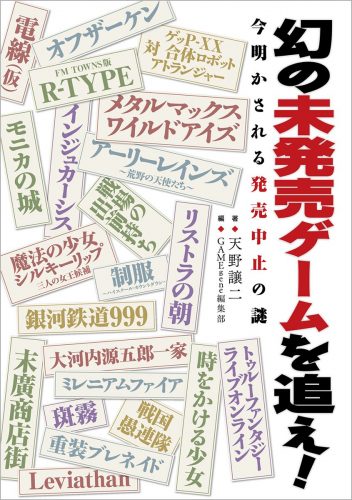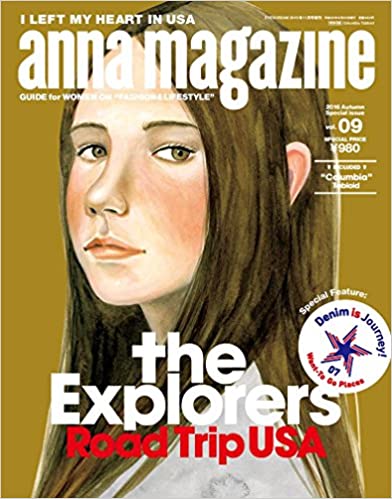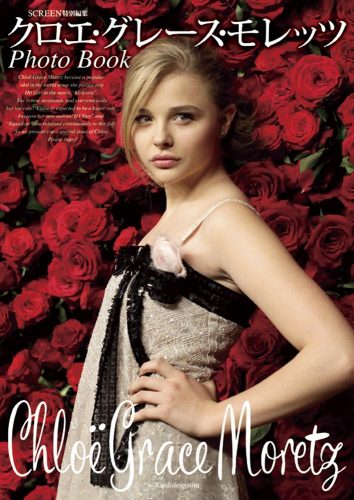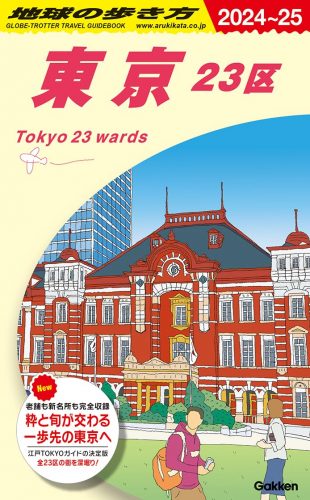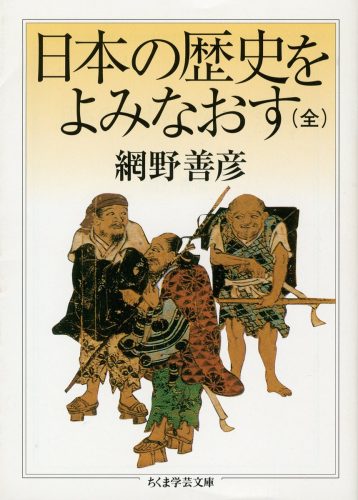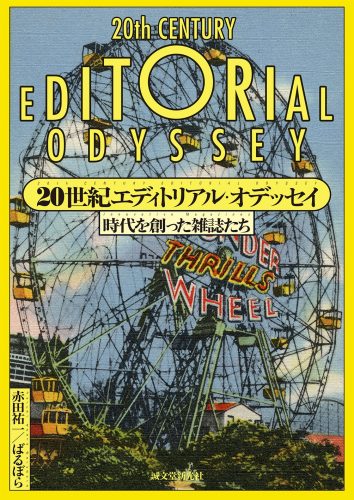土佐の、おそらく仁淀川と思われる、贄殿川流域の山村を舞台にした大河小説だ。かつて士族だった村の名主に嫁いできた、その容貌から猿嫁と呼ばれた蕗の、明治から昭和に及ぶ90年あまりの人生を描いている。明治初期、更に山深い村で生まれた蕗は自由民権運動が盛んな頃にこの村に嫁いできた。夫のその仲間も自由党として政治運動に熱中している。そんな中、出戻りの義姉が父なし子を身ごもり、産んだ。姑は殺そうとするが、赤子は墓に埋められる直前に息を吹き返し、蕗は自分の子として育てようとする。そんな中自由党を弾圧しようとする官憲との騒乱が起き…というのが第一部。第二部では、村人たちにも日露戦争の召集令状が届く。時勢に翻弄されたり、家を守ろうと自分の気持ちを押し殺したりしながら、それでも逞しく生きていく女と男たち。やがて義姉の子は家を飛び出し、生んだ娘も嫁いでいくが、蕗は道祖土家で暮らし続ける。カッパや長宗我部に追われた落ち武者、先祖から伝わる踊りや祭り、大正から昭和にかけての農村短歌運動、夜這いといった農村の暮らしと民俗が近代日本の戦争や動乱と混じりあい、名もなき庶民の壮大な物語が紡がれる。六つの章どれもに時代の奔流と濃密な性と生死が描かれるが、特に第二章の猿猴ヶ淵のラスト1ページが圧巻だ。昭和恐慌、太平洋戦争、戦後の高度経済成長もこの村や家をを巻き込み、変えていく。ずっと変わらなかかった懐かしい過去から変わっていく懐かしさのない未来へ、私たちはどこへ行こうとしているのか。鎮守の大樟と道祖土家の伝説に出てくる猿が一族の生と死を見守り続けているようにも見える。時を経る中で、書かれた事件が誇張されたり尾ひれがついていく様子も面白いし、どの登場人物も存在が際立っている。小説の舞台となった仁淀川流域の、秘境と言ってもいいような山間の村に行きたくなる小説だ。
/
2021/07/16