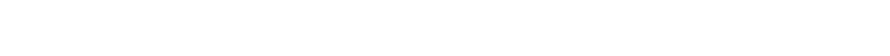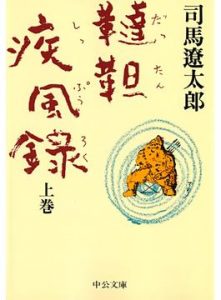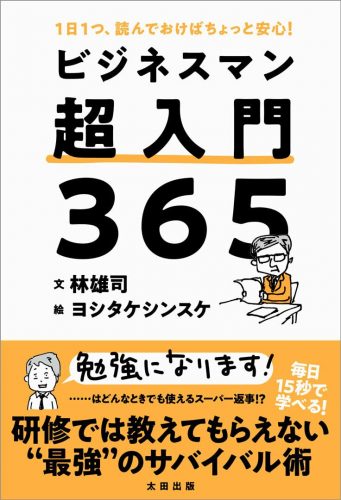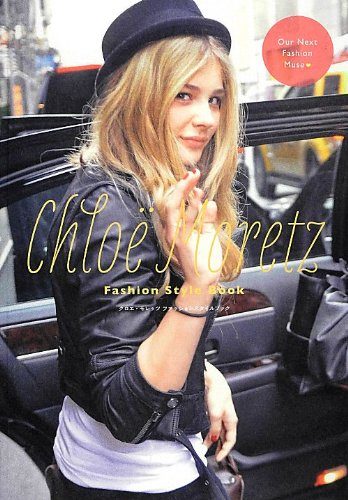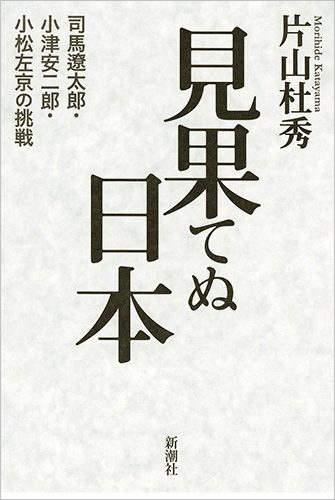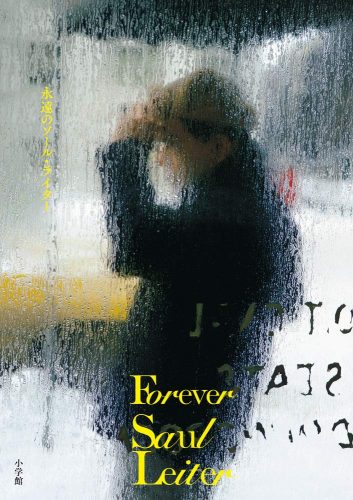司馬遼太郎の作品は小説に限っても多くあるが、そのほとんどが1960年から1980年代の、わずか20数年に書かれている。その最後の小説が『韃靼疾風録』だ。以降、司馬は小説は書かなくなり、随筆か紀行文のみになる。
筆者はこの『韃靼疾風録』が司馬遼太郎の作品の中で最も面白いと思う。
ボーイ・ミーツ・ガールであったり、ファンタジー要素やキャラクター描写が中心だったりと、ライトノベルっぽさもある。
江戸のはじめ、長崎平戸の侍・桂庄助が漂流してきた韃靼国の姫君を助け、ともに海を渡り夫婦となるまでが〈上〉のあらすじだ。鎖国する日本から飛び出し、王朝が明から清へと代わる激動の中国大陸で翻弄される様は冒険小説の主人公のようでもある。
典型的な日本の武士の思考を持つ庄助が、明の軍人や李氏朝鮮の官僚と言葉を交わすことによって儒教の価値観を浮き彫りにさせているが、巨大な儒教の価値体系を信奉しているはずの人々も、実際の行動では国を裏切っていたり不正蓄財をしていたりして、その落差の大きさには日本にはないスケール感がある。
また、韃靼の姫君・アビアが、『竜馬がゆく』に出てくるお田鶴や千葉さな、おりょうにも似ている勝ち気なキャラクターで可愛らしい。なんとなくだが、司馬の小説は女性が活躍しているものの方が読んでいて楽しい気がする。
日本を発ち10年近く経って、ようやく庄助がアビアと結ばれるまでで上巻が終わる。
下巻では明王朝が滅び清王朝が建てられる、いわゆる明末清初の動乱が描かれている。清の一介の客将にすぎない桂庄助はあまり出てこず、明の宮廷内の話が続く。余談も多い。だがそれがつまらないかというと、日本にはないスケールの大きな官僚や宦官の不正、腐敗、混乱が描かれていて驚かされる。
億を越える人々が生み出す繁栄は、その繁栄が大きければ大きいほど没落するときの悲惨さは際立つ。偉大な明王朝は、最後は皇帝の自殺によって終わる。李自成の反乱軍に次々と宦官や将軍が寝返り、北京の城門も寝返った宦官によって開けられ、反乱軍が殺到したという。その李自成を打ち倒したのが、呉三桂の内通によって開けられた山海関から華北中原に殺到した清軍だった。
王朝の交代も劇的だし、中華思想による価値観の交代も劇的だ。中華思想による論理では野蛮で未開の部族とされていた韃靼族の皇帝たちは、中国史上最も英明で、最も儒教を敬ったし、中国の版図を最も大きくした。人口も4億人を超えたが(4億もの人々を数え、記録に残した官僚制もすごい)、やがて世が下るにつれて歴代の王朝のように腐敗し、19世紀にはイギリスにも日本にも負けるなどしてついに20世紀初頭に滅びしてしまう。明治維新後の日本は、そうした国勢が衰えた清末しか知らないが、日本が鎖国していた江戸時代、韃靼族の皇帝は史上最もうまく中国大陸を統制してきたことは、もっと知られてもいい気がする。
ただ漢民族はラーメンマンのような辮髪だけは嫌だったみたいで、調べてみると辮髪を拒んだり清に反抗したため、見せしめのように数万人単位の弾圧や虐殺が起きていたりもする。
スケールの大きな中国大陸の王朝交代を一人の日本人の目から眺めた小説とも言えるし、そうした激動の時代を生き抜いた庄助の姿も清々しく、読後感が心地よかった。