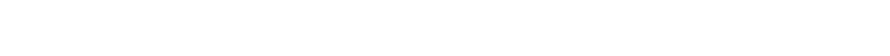第二次世界大戦で日本が敗戦後、約7年間に渡りアメリカの占領を受けていた、ということをご存知だろうか。日本政府は、米兵の性暴力から良家の子女を守るために、米兵専用の慰安所を設置する。慰安所に集められた女性は「お国のため」に厳しい労働環境に晒された。占領下の日本は、ほぼすべての出版物、レコード、ラジオ、手紙、電話までもがGHQの検閲を受け、十分な客観的資料が残っていない。だが、米兵専用の慰安所が日本政府主導で作られたこと、そして自殺者が出るほど厳しい性労働に晒された女性たちがいたことは事実である。
歴史学者・平井和子は、「お国のため」に差し出された女性たちの声を拾い上げようと慰安所のあった地域で聞き取り調査を重ね、これまでに5冊の本を出版。山川菊栄賞や青山なを賞を受賞するなど、これまでほとんど光が当たることがなかった占領期の性にようやく光が当たろうとしている。
戦後80年を迎え、占領期のことを知る人も歴史の舞台から去ろうとしているいま、なにを思うのか。どうしても話を聞きたいと思い静岡まで伺った。
文・インタビュー/高橋数菜
――本日は貴重なお時間ありがとうございます。僕が『パンパン』の方々の存在を知ったのが去年なんですね。ネットサーフィンをしていて、アメリカ兵と若い日本人女性が一緒に写っている写真があって。それに対して誰かが「こういう女性は『パンパン』っていうんだよ」みたいなコメントをしていて。『パンパン』ってすごい名前だなと思って。絶対に正式名称じゃないだろうと思って調べたんですけど、蔑称でもありほぼ正式名称で。
「差別用語なんですけど、もう歴史用語ですよね」
――だからすごい名前だなと思って。『パンパン』について書いてある本ないかなと思って行き着いたのが『占領と性: 政策・実態・表象』(インパクト出版会、2007年)だったんですね。この本を読んで非常に打ちのめされたといいますか。僕、 1986 年の生まれなんですけど、僕がいた小学校中学校では従軍慰安婦なんかなかったっていう教育を受けたんですね。
「はいはいはい」
――だから従軍慰安婦はいたんだっていう驚きと、終戦記念日は 8 月 15 日であると疑いようもなく思っていましたし、アメリカは日本を占領していたっていう意識もまったくなかったですし、日本のことをまったく知らないなあと思ったんですね。この本のまえがきやあとがきに「本書はまだ研究の途中である」と書かれていて、その後この研究がどうなったのかなって思って調べたんですけれども、ホームページの更新も止まっていたり、執筆された方の何名かは亡くなられていたりして、この研究がその後どうなったのかなっていうのをまずお聞きしたいなと。
「ありがとうございます。私もいま、話を聞いてびっくりしました。先生が教育の場で『従軍慰安婦はウソだ』ということをお話されたと。学校は公立?」
――公立です。
「でもそういう空気の時代もありましたよね。この『占領と性』をまとめた恵泉女学園大学平和文化研究所は代表者が荒井英子さんだったんですが、いちばん先に亡くなっちゃったんですよ。その後もずっと研究を続けていく予定だったんですけども、中心人物の荒井さんが亡くなったので、空中分解というか、そのあと続けて奥田暁子さん、加納実紀代さんが亡くなられたので、私だけが続けることになってしまいましたね」
――いつ頃に空中分解になったんですか?
「この本を出したあとすぐです。本を出したのち発病され、3年ほど療養されたのですが、残念ながら亡くなられて……」
――この本はどういった経緯でできたんでしょう?
「私は途中から参加したので、経緯はよく知らないんですけども、2000 年ぐらいから恵泉女学園大学でキリスト教界の人たちの戦争責任みたいなものに向き合っていこうみたいな話になったらしいんですよ。そのなかで占領期の慰安所に対してキリスト教界がどういう態度を取ったのかを知りたいね、っていう話になった。それで私は占領期のことを修士論文で書いていたので、加納さんに占領期の専門家にきてほしい、って言われて入っていったという感じですね」
――朝日新聞のインタビューで拝見したんですけど、結婚を機に静岡に引っ越されて教師のお仕事をお辞めになられたと書かれていて。
「はい、最初は東京に就職してたんですけど、夫が静岡の教員になったので、しかたなく辞めて伊豆に来たんですね。大学生の時の専攻は地理学だったので歴史をやるなんて思っていなかったんですよ」
――そこで「男性は仕事、女性は家庭」という固定観念に興味を持たれたと。
「そういう役割分担がいつできたのかなっていうか、自分自身への問いですよ。なんで私のほうが結婚の時に仕事を辞めるのかな、なんで私のほうは名前を変えなきゃいけないんだろうって。当時はそれに誰も答えてくれなかったんですね。女性学もでき始めた頃だったので、じゃあ自分で歴史に聞いてみようって」
――そこで静岡の人に調査をされて、『パンパン』の人たちのことも初めて知るんですか?
「いえ、その頃は占領期のことはまだ聞けなくて。静岡大学の修士課程に入った時に御殿場を調べて、御殿場にはたくさん『パンパン』が集まっていて、『パンパン』の名簿とかもあったんですね。それが 1997 年ぐらいですね」
――そこで衝撃を受けてこちらの道に進まれたと。
「うん。そうですね」
――教師は何歳くらいまで続けられたんですか?
「修士課程に入ったのが 1997年なのでその時に辞めたのかな。最初、東京で一般企業に勤めてたので。東京で教員の採用がなかったんですね。なので静岡にきて教員採用試験を受け直して教師になるっていう感じです」
――一般企業ではどういったお仕事をされていたんですか?
「地理学科の卒業だったので、地質検査の会社に入ってました。そこで3 年働いて、結婚で西伊豆にきて、そこで自分のモヤモヤを解決するために地元のおばあさんたちのライフヒストリーを聞いたり、女性史の本を読み漁ったり……みたいな感じですね」
――結婚の前まではそういったモヤモヤってなかったんですか?
「大学までは男女平等だったんでなかったですね。社会に出て初めて。だからお茶汲みがあることにびっくりして。お茶汲み拒否っていうのをやりましたね。で、組合の中に女性部を作りました」
――すごいですね。
「だから、もといた会社では伝説になってるらしいんですけど、こんな跳ねっ返りがいたとか(笑)。雇用機会均等法ができる前ですので、女性は夜 8 時以降は働いてはいけないっていう『母性保護規定』があったんです。なんですけども、忙しいから 夜10 時ぐらいまで働くんですよね。そうすると『おい、お前ここからは女じゃないからな』とか言われて毎夜働かされて。お風呂に行けないじゃないですか。当時、銭湯は夜 11 時ぐらいまでで。家に帰ったらもう銭湯が閉まってるの。それが悲しくて、会社のボックスにお風呂セット置いて、裏の銭湯に行ってきま~すとか言って、帰ってきて仕事してましたね」
――その後、教師になられるんですよね?
「そうですね、東京でも教員にすごくなりたかったです。だから採用がなくても毎年採用試験を受け続けてました。採用されなかった理由は女性だったからって自分では思ってます。社会科の女性教員はいらないっていう。静岡県にきても、社会科の女性教員は私だけでしたね。国語とか音楽は女性教員が多いんですけど、教科によってジェンダーの偏りがあって。うちの夫は同じ大学出身だったんですけども、社会科の教員の採用があるわけですよね。だからすごいジェンダーギャップを感じました」
――募集自体は男女を問わずだけど、受かるのは男性だけみたいな。
「そうですね。入口では男女平等をうたっているけど、採用や雇用の仕方ではジェンダーで振り分けている……」
――『占領と性』の筆を取らせたのは、性だったり、この本に書かれているように「良い占領なんて存在しない」という意思だったりなんでしょうか。
「私と加納さんはすごく議論しましたね。私は……この占領は、良い占領ではなかったっていうことを、女性の体験から捉え直したいという思いはあったんですが、加納さんたちは戦後の女性解放や民主主義、女性参政権獲得などあるので、占領体験は男性にとっては屈辱、女性には解放だったと捉えていました」
――そうだったんですね。この本は良い占領はなかった一色なのかなっていう印象を受けたんですけど。
「だからいつもみんなで議論しながら書いた本だなって思っています。毎回みんなでホットな議論をしていましたね」
――あと書きにはみんなで合宿に行ったと書かれていて、和気あいあいとしていたのかなと思ってたんですけど。
「合宿3回は、とても楽しかったけれども、常に喧々諤々やっていましたね。その厳しさのなかで、本書が生まれたし、一方、残念ですが途中で抜けたメンバーが何人かいらっしゃいます。」
――なるほど。僕はこの本を読んですごく衝撃を受けたんですけど、2014年の『日本占領とジェンダー : 米軍・売買春と日本女性たち』(有志舎)を読んで研究が進んでるって思ったんですね。さらに2023年の『占領下の女性たち 日本と満洲の性暴力・性売買・「親密な交際」』(岩波書店)を読んで、さらに研究が進んでいる、と感銘を受けまして。どうやって研究を深めていったのかなっていうのをお伺いしたくて。『占領下の女性たち』に公文書館で RAA開設の指令が残っていたって書かれてたんですね。実際に僕も検索してその文章を読んだんですけど、当たり前なんですがすべて手書きで、読むのすら大変で。しかもあの文書ってタイトルに慰安婦とか入っていないので、だからまず見つけるのが大変だなって思ったんです。
「大学院に行って、先生から資料の見つけかたを鍛えてもらったんだなと思います。敗戦直後に出されている内務省からの国民への注意とか、各都道府県に出された指令とかを丁寧に読めば、『一般女性』は保護しなければいけないとか、『性の防波堤』=『慰安所』のようなものを作れみたいなものがあるはずだからって。嗅覚を鍛えられたっていうか。恩師の吉田裕先生や荒川章二先生からは『歴史家は文書を探さなければ』って教わりました」
――僕が衝撃を受けたのが昔の公文書って手書きじゃないですか。あれをひとつひとつ解読していくわけですよね。
「慣れますよ(笑)。読んでれば慣れますし、関係するところがボわっと浮き上がって見えてくる。『慰安』という文字とかね」
――でもたぶん、平井さんの前にそれに気づかれた方がいないからこそ発見に繋がったんですよね。
「はい。御殿場の『風紀問題』(「パンパン」たちに対する住民調査など)に関する貴重な資料は、静岡県史編纂室で見つけたのですが、その前に他の先生の『閲覧しました』という付箋が付いていたのですが、スルーされていました。研究者によって何が重要か、その人の視点が問われると思います。その資料のもっと詳しいものが、現地・御殿場市に残されていて、そこで『パンパン』たちの『身上調査一覧』を見つけたときは、震えました。しかし、内務省の『進駐軍に関する注意』の文書は、先に国会議員の吉川春子さんがそれを使って国会で質問されたりするんですね。公文書館を見たりとか、GHQ 文書見たりとか。いろんな人たちの先行研究があって、その上に私の研究もあるなと思います」
――この本で蘭信三さんが、「孤独と不安に苛まれながら研究をされていた」とあるんですが、みなさんそういう心を抱えながら研究をされているんでしょうか。
「ほとんどみんなそうだと思います。いまも、若手の研究者の卵(院生)たちは、みんな孤独で、果たして自分の研究テーマはこれでいいのだろうか、と悩みながらやっていると思います。私自身もこういう研究をやる人は少なかったので、特に男性の偉い研究者からは『なんで性のことなんかをやるんだ』って。それはすごく差末なことであって、経済とか政治とか、そういう大文字の歴史が社会を動かしてきたと。占領期の御殿場の歴史に触れることに対して、なんでそんな地域の恥のようなことをほじくるのかみたいなことを言われました。だから修士論文にも自信がなかったです。メインストリームの女性研究者からも『私は性のことはやらない』って面と向かって言われましたので、孤独でしたね」
――ああ、そうなんですか……。
「関西で茶園敏美さんが『パンパン』のことをやってるっていうのが心の支えで。向こうも関東で平井さんが『パンパン』のことをやってるからっていう風に自分を励ましてたっておっしゃってました」
――平井さんが性に対して聞き取りをされる時に、なかなか語りたがらない方もいらっしゃると思うんですね。
「そうですね。性に関しては二面ありますよね。出産などのリプロダクティブなことは女性が行くと積極的に語ってくださるけれども、性暴力被害に関しては語りに抑圧がかかる。私は駆け出しのころ、伊豆にきて、片っ端からおばあさんたちに話を聞いてたんですよ。そうすると民俗学をやっている男の人たちが、どうして平井さんが行くと僕たちが聞いてこなかったような出産や生理とかを聞けるんだろうって言うんですよ。それは女性が女性に語りやすいからっていうジェンダーがあるとは思うんですよ。でも性暴力みたいなことに関しては、岐阜の黒川開拓団の佐藤ハルエさんが『性接待』について最初に語ったのは猪股祐介さんっていう、当時まだ院生だった男性です。だからジェンダーに関わりなく、一生懸命その人の証言を聞いてくれる人があれば、語りたかったんだと思うんですよね。性って人権のいちばん大切なところだと思っていて。それを男性本位のポルノグラフィーっぽく表してきたこと、消費していくことに対しては抵抗感があるんですよ。一方で、女性史・ジェンダー史をやるものは性的な快楽とか性的なエロスとかもタブー視しないで聞いていかなきゃいけないって思っています。その辺の線引きのところはすごく危ういところなのかもしれないんですよね。『赤線』の人に話を聞きに行くときにはすっごく気を使いました。手紙で申し込むのがいいのか、電話がいいのか、それとも誰か住んでる人のツテを頼って聞くのがいいのか、飛び込みで行く方がいいのか……電話をするだけでも 3 日ぐらい悩みましたね。何時頃に電話をすればとか。Hさんっていう方に行き当たったんですけども、ちょうど 2 時ぐらいに電話をしたら『いま、うちに誰もいないからすぐ来て』っておっしゃった。家族がいないときだったら、語れる。息子さんがいらっしゃらなかったりとか。相手にとっていちばん話しやすい時間とか場所っていうのはどこか、いつもいつもすっごく悩みますね。性売買に関してはタブーはまだまだ多いですね。熱海はいつも明るくて、すごく元気づけられるんですけども、あっけらかんと語れることでもないんですよね。Hさんも最初のうちは『自分のうちはボットル屋だった』っておっしゃってたんですけども、話をよくよく聞いていくとパンパン屋だったことがわかるとか。それから吉原の遊郭で働いてた人が熱海でお店を持たれていて。彼女にパンパン屋の経営者だったっていうことで話は聞いてもいいけども、ご自身が吉原で働いていたことは聞いちゃだめよって」
――……すごいですね。
「はい。この本も、校了して、岩波書店さんから『明日印刷に入ります』って電話をいただいた時に、私の手の届かないとこに行っちゃうと思って、3 週間ぐらい体が悪くなりました」
――もう引き返せないところまできてしまった、みたいな。
「はい。おひとりおひとりには原稿を見せて、書いてもいいですよって承諾書に署名もいただいてるんですけども、だけども気がつかないところで、傷つけたりする人があるんじゃないかとか思って怖かったですね」
――今年、戦後 80 年じゃないですか。ご存命のパンパンの方がいらっしゃる最後の時代だと思うんですよね。
「この本の第5章に出てくる朝霞の『パンパン屋』で育った『金ちゃん』が70年の時を経て偶然出会った元『パンパン』だった『あぐりさん』をゆくゆくは私に会わせてくれようと思ってたらしいんですけど、急に姿を消しちゃったんですよね。だからなんか感づいて、話すの嫌だなと思われたのかもしれない」
――この本では『あぐりさん』はコロナで亡くなられたと。
「そういう噂も金ちゃんは聞いてるらしいんですけど、途中から金ちゃんがメモを始めたんです。紙芝居にしようと思って。だから何かしら気が付かれたのかな、と思ったって」
――僕が想像してたよりも繊細なバランスの上に成り立ってる本なんだなって思いました。
「そうですね。私もほんと、軽く思ってた部分があるんですよね。私もおおらかでおっちょこちょいなもんですから。だけど、本を書く時に熱海の人から承諾書をいただいた時に、私の名前は間違いやすいから間違えないように書いてね、っておっしゃった方が、印刷所に入ったあとで電話を寄越されて。この SNS 時代に名前が広がると怖いからやめてって言われて。で、すぐ岩波さんに電話したらまだ間に合って。間一髪で匿名にしました」
――平井さんは 1955 年の生まれですけども、その当時って戦争の爪痕とか『パンパン』の方々がいらっしゃった空気とかはどのくらいあったんでしょう。
「『パンパン』って聞いたことなかったです。生まれは広島ですので、原爆の語りはたくさん聞いて育ちましたけど、米兵相手の性売買女性がいたっていうのは一言も聞かずに育ちましたね」
――平井さんのご両親は戦争を体験された世代だと思うんですけれども、家庭で戦争のことが話題になることってあったんでしょうか。
「父は広島の爆心地に住んでたんですけど、8月のちょっと前に招集されて東京にきてたんです。母は田舎の生まれですので、原爆被害の話は聞きましたけど、戦争自体はぜんぜん聞いてないんですよね」
――僕、 86 年の生まれですけど昔、道端に手とか足とかがない軍人さんがお金くださいってやっている光景をよく見た記憶があって。でもいつの間にか見なくなったなっていう感覚があって。戦争特番なんかも僕が子供の時は年中やってた気がするんですけど、いまだと終戦記念日くらいしかやらないようになっちゃったなって思っていて。いまの子たちにとって戦争ってより遠いものになってるんじゃないかなっていう感覚があるんですね。平井さんもいろんな生徒さんを教えてきてそういう感覚ってありますか?
「86年生まれの高橋さんの世代でも、まだ、道端に傷痍軍人さんが居られたとは、驚きました。夏に戦争物を放送するというのは、8月ジャーナリズムですよね。授業とかで、アジア・太平洋戦争や、軍『慰安婦』のことをやると『おじいちゃんやひいおじいちゃんに聞いておけばよかった』って生徒は必ず言いますね。中国戦線におじいちゃんが行ってたから『慰安所のことも聞いてみればよかった』とよく言いますね。ただ、アジア・太平洋戦争も彼らの世代には、もう歴史になってますよね。西南戦争とか、日清・日露戦争、満洲事変、太平洋戦争と暗記する、みたいな」
――それは教えていて寂しい気持ちを覚えたりしますか?
「戦後80 年経ってますからね。身近な人から聞くっていう貴重な体験はできないけども、その分、客観的に見れるようにもなるんじゃないかな。身近な人の体験談は、どうしても偏っちゃうじゃないですか。私は広島で育ったから、周囲の体験談は被害者意識ばっかりなんですよ。だけども、なぜ広島に原爆が落とされたのかっていうことを大学生ぐらいになって考えると、広島が近代以降軍都で発展してきて、日清戦争の時は大本営も置かれ、そしてアジア侵略に対して兵士を宇品港から送り出した場で。どうして被爆者に朝鮮の人やアジアの留学生が多かったのかとか、強制的に労働者として動員してきた人たちもいたって思うと、やっぱり近現代の日本帝国のありかたとかが広島を通じて浮き上がってくる。原爆を落とされるときには、軍都だったとこが狙われたんだな、だからその街の人たちの生き方とか盛業のあり方によって戦争の被害者になったりするんだなって、歴史が因果関係と繋がって見えてくる。被害者意識だけだとね、視野が狭くなりますよね。犠牲者主義ナショナリズムは、国家間の紛争の元になりやすい。まさに、現代のイスラエルがそうですよね」
――僕、岐阜の出身なんですけど、各務原にも『慰安所』があったってこの本で初めて知って。なんで各務原なんだろうって思ったら、あそこに自衛隊の基地があるんですよね。だから元々米軍基地があったんだろうなって。いまの各務原に米軍基地や『慰安所』のニオイがまったくないんですよ。だからめちゃくちゃ意外で。
「各務原は跡形がない感じですよね。福生とかだと残ってるんですけどね。地域によって違いますね。キャンプ・ドレイクがあった朝霞もみんなびっくりするんですよ。あんなに『パンパン』の人たち集まってたんですか、近くに住んでたのにぜんぜん知りませんでしたって。各務原と同じく朝霞も現在自衛隊の駐屯地になっています」
――いまでも『パンパン』の方がいらっしゃってそうな地域とかってあるんでしょうか。
「金ちゃんも大泉学園まで足を伸ばしたとか言ってますけど、きっとね、熱海だってね……私は熱海の住民にならないと本当のことは聞けないなと思いました。熱海のなかで暮らして、今日は暑いですね、とかおはようございます、とか言ってるうちにわかってくるんじゃないかって。『赤線』を取り締まっていた警察の人にも言われたのですが、『むかしパンパンをしていた人を今でも町で見るけど、あんたには言えないな』っておっしゃったから。出会えないんですよね。いや、もう出会ってるのかもしれないんですけども、本人は明かしてないかもしれないし」
――この元警察の方に代わりに聞き取りをお願いするのはダメなんですかね。
「もう亡くなってますね。この方にインタビューしてた時は 2004 年だったので。あと『占領と性』を書くときに間に合わなかったのが保健婦さんなんですよ。『コンタクトトレーシング』っていう、性病に罹った米兵が出たとしたら、その米兵の性病の感染源を日本側の女性だと決めつけて、米側は『接触者調査』というのを保健所に義務付けるのです。それで保健婦さんが、米兵の証言を頼りに女の人たちを訪ねていったら、『パンパン』たちがシングルマザーだったとか、重度の性病だったということを手記に書いてらっしゃるんですけど、その方々がちょうど亡くなってしまって、直接聞きたかったのに間に合わなかったなって」
――時間との戦いじゃないですけど。
「そうですね。熱海は大火で資料が焼けているので文書が残ってないから。人づてでやっていくしかなかったですね」
――平井さんが占領期のことを書くいちばんの衝動って「良い占領なんてなかった」ということを伝えるためですか。それとも歴史に埋もれた女性たちの声を浮かび上がらせるためですか。
「両方ありますけども、男性リーダーたちによって、守るべき良家の子女と、差し出してもいい女性とで女性が二分化されるじゃないですか。内務省警保局の秘密文書も営業に充てる女性は芸娼妓者っていっているでしょ。女性が家父長制によって二分化されてたまるか、みたいな。女性たちで連帯したい、という気持ちが強くあって。その、家父長制意識を女性も内面化させて、二分化されたほうの良家の子女は芸娼妓者たちを差別するんですよ。もうたまらないですよね。とくに満州の引き上げの時に、ソ連兵に女を出すように強要されて、『一般の女性』や母親が連れ去られようとするのを見かねて、性売買の女性たちが『私が行きます』っていうじゃないですか。それもたまらないですよね。その人たちのことを歴史に書いておかずにはいられない、って。それがありますね。あの人たちのことを絶対に歴史に刻むのが私の仕事だって。『占領下の女性たち』の2章を書いたときは……あの、私、性暴力被害なんかも淡々と書くタイプなんです。でも2章を書き終えた時はこみ上げてくるものがありましたね。満州のね、『一般女性』を見かねて、私が行くべきだみたいなことを性売買女性は思うわけですよ。『一般女性』は助けられたって思って、彼女たちをのことを拝んでいる。忘れないでいるんですけど、男性たちは不都合な歴史なので忘れてしまいたいとか。なので、どこにも彼女たちの声が残らない。だから、それはいけないなっていうのがありますね」
――『占領下の女性たち』の冒頭でも書かれた、コロナ禍で性風俗の人には給付金が出されないっていう決定に対しても平井さんにとっては。
「労働者から外すなよ、みたいな思いがあります。ずっと近代史のなかで労働者たちが連帯をする時に、性売買女性や芸娼妓の人たちを外してきたんですよね。ところが戦時になると、その人たちが国防婦人会に入れてもらったらすごい喜ぶんです。一般女性と同じように、私たちもお国のためにできることがあるって。差別を受け、疎外されてきた存在ゆえに、喜んで国策に協力させられていくメカニズム。性差別を受けた人たちだから、余計に国に協力することによって一般の人たちと同じになりたいみたいな、心理が働く。そういう差別構造をなくしていきたいっていうのがありますね」
――日本が占領されてRAAが作られたことに対してすごく怒っていますよね。
「RAAを作った人はね、あれのおかげであの性暴力減ったんだって言いますけど、私は逆に増えたと思っています。戦争に勝利したら敗戦国の女性を安く買えるんだ、自由にしていいんだっていうことを教えているみたいな気がして」
――近代の戦争で敗北した国が占領を受けなかったケースってあるんでしょうか。
「みんな占領されてますよね。軍事占領自体が、暴力性を伴いますよね。占領のあり方っていうものも、国際的にルールができないといけない。国連も戦勝国側が常任理事国ですので。第二次世界大戦後にそういうことが作れなかったっていうのは、私たちの民主主義の弱さですかね」
――平井さんがRA Aに反対とは承知なんですけど、でも日本が占領を受け入れた時点でバッドエンド確定だったんじゃないかなって思っていて。
「日本にペリーがきた時から唐人お吉を差し出すじゃないですか。そうやって性接待ばっかりするのをずっと伝統的に繰り返してる国だから……ポツダム宣言受諾の時に、占領においては絶対に暴力的行為、特に女性への性暴力は厳しく禁じてほしい、と確認してほしかったと思います。それどころか先回りしてね、『おもてなし』を準備しているっていうのは情けないな、って」
――近年、開拓団のサバイバー女性が声をあげたりとかっていうのは、社会が変わっていっている証しなんでしょうか?
「亡くなる前に語らずにはいられないっていう思いもあったでしょうし、韓国の慰安婦女性たちが発言し始めて、あの人たちがあんなことを言うんだったら私たちだって同じ体験だよね、っていう認識を、聞き取りに訪れた猪又さんにおっしゃったらしいんですけども、そのような韓国のサバイバーの名乗り出も背中を押したようです。性暴力を受けた人が恥ずかしいんじゃなくて、それは大きな大きな構造的な犯罪だったっていうのが共有されるようになりつつある。やっぱり時代が変わってきつつあるんでしょうね」
――お話を伺ってると、僕が教えられてきた教師の異常さというか、そういうのを改めて感じますね。当時はインターネットもないから正解にたどり着かないですし。
「90年代の慰安婦問題の時は国内外ですごい論争になりましたもんね。金学順さんの名乗り出以降、『慰安婦』否定派の人たちから、あの人たちは売春婦だって言われて、言われた方は公娼じゃないって、水掛け論みたいになってすごい不毛な、不幸な論争だったなと思いますね」
――平井さんの著書はさまざまな賞を受賞されていますけど、こういった賞は孤独な作業に対する、孤独を跳ね返すような要素になったりするんでしょうか。
「認められたと思いました。嬉しかったですね。選んでくださった先生がなんで選ばれたかっていうの言ってくださって。資料をよくぞ集めました、とか、視点のバランスがいいと評してくださいました。こういう面もあるし、こういう風にも見えるし、っていう。ひとつに決めつけないで、でも筋は構造的な性暴力っていうものはしっかり立てて、ブレない。で、“親密な交際”もあるっていう性暴力にグラデーションがあることも見逃していない、と言われました。この分野は研究者が少なかったので、孤独に苛まれつつ、自分はこんなんでいいのかな、みたいなことを思ってずっとやってきましたけど、いまは院生たちのなかに占領や性をやる学生が増えてきたんです。すごい嬉しい」
――こういった本に対して担当編集さんはどういったサポートをするのでしょうか。
「今回の岩波書店のおふたりの担当は知り合いだったので、自分で原稿を持ち込みました。それを受け取ってすごい悩まれたんですよ。この問題って地雷を踏むようなテーマが 3 つぐらいあって。『慰安婦』も『セックス・ワーク』も『満洲』も入っているので。下手にいい加減なことを書くと、どこからどんな批判の矢が飛んでくるか分からない。平井美帆さんっていう方ご存知ですか?」
――はい。
「平井美帆さんの『ソ連兵へ差し出された娘たち ―証言・満州黒川開拓団』の本は賞を取ったんですけども、実は倫理違反もありました。本人に許可なく実名を出していたので、ものすごい問題になって。遺族会の人たちが、もう語り部をやりたくない、とかおっしゃるぐらいダメージが強かったんですよ。開拓団のことは私の本にも入っているし。だから岩波さんは編集会議を通すまで1年近くかけて熟慮されたようです。それと岩波の鬼の校正、はじめて体験しましたね。すごいとは聞いてはいましたけど」
――岩波で企画が通らない間に、ほかの出版社へ持っていこうとは思わなかったですか?
「なかったですね。それでも早く出して欲しいなとは思いました。その間、ほかの出版社から2 冊ぐらいRAAに関する新書が出て、男性の方が何の痛みもなく書かれている気がして……焦る気持ちはありました」
――出版社側の人間からすると本当に出しづらいテーマの本ですよね。なので、本当に世に出てよかったなってすごい思います。最後に下世話な質問かもしれないですけど、『パンパン』の方に会えたらなにを聞きたいですか?
「つらかったのか、どういう思いでパンパン家業をしていたのか聞きたい。あぐりさんは夜の星を数えて我慢してたっておっしゃってますよね。あぐりさんの言葉しか聞いてないんで、本当はどうだったのか」
――でもたぶん人の数だけ答えがあるでしょうね。これも僕の話になっちゃうんですけど、風俗をされている女性に話を聞く機会があるんですね。彼氏から「風俗嬢をやめて」って言われるほうが嬉しい人もいるし、「風俗を続けて欲しい」って言われるほうが嬉しい人もいるんですよ。だから風俗嬢を好きでやってる人もいれば、やめたがっている人もいるんだなっていうのを聞いていて。だからたぶん、あぐりさんみたいな人もいれば、楽しいっていう人もつらいっていう人もいるんだろうなって。
「でも、それは彼氏に依存している、あるいは搾取されている、ということで決定権を彼氏に委ねてるということでは根っ子では同じでしょ。『パンパン』も『かわいそう言説』、『犠牲者言説』に回収されない人がいるんですよ。静岡新聞に載っていた1950年代の『夜の女』へのインタビューなんですが、『こんな女に誰がした』っていう歌が当時、流行っていたんです。でもそれは嘘だ、私はこの仕事を真剣にやっているって。その言葉もね、肯定的に受け止めたいと思うんです。だから犠牲者にも回収されないしっていうエージェンシーが感じられるような言葉を発揮してる人にも会いたい。いま学会では、セックスワーク論と、性売買は性暴力だっていう人たちとに別れて深い対立があって、それは悲しいことだからそこに橋をかけるような実態的な歴史学をやりたいと思いますね」
information
平井和子
1955年広島市生まれ。
一橋大学ジェンダー社会科学研究センター客員研究員
専門は、近現代日本女性史・ジェンダー史(社会学博士)
静岡県東部の中学校・高校の社会科教師を経て、静岡大学、大妻女子大学などで非常勤講師。一橋大学ジュニアフェローを経て、現職。
主著・共著書
恵泉女学園大学平和文化研究所『占領と性 政策・実態・表象』インパクト出版会、2007
『日本占領とジェンダー 米軍・売買春と日本女性たち』(山川菊栄賞受賞)有志舎、2014
上野千鶴子・蘭信三・平井和子『戦争と性暴力の比較史へ向けて』岩波書店、2018
『占領下の女性たち 日本と満洲の性暴力・性売買・”親密な交際“』(女性史 青山なを賞受賞)岩波書店、2023 など。
『占領下の女性たち 日本と満洲の性暴力・性売買・”親密な交際“』にも
「金ちゃん」の紙芝居上演会:1950年代、米軍基地・朝霞の街の「ハニーさん」たち
「パンパン」たちに部屋を貸す「貸席屋」で育った、「金ちゃん」(田中利夫さん、1941年生まれ)が、日記と抜群の記憶力をもとに描いた「紙芝居」の上演会が2025年6月7日に上智大学四ツ谷キャンパスで行われます!
2025年6月7日
東京都千代田区紀尾井町7−1
上智大学四ツ谷キャンパス 6号館3階305教室
参加無料 後日動画配信あり
https://kamishibai-kinchan0607.peatix.com/